| 閉じる |
| 【発明の名称】没水体積の浮体発電 【出願人】 【識別番号】591177783 【氏名又は名称】浦本 鴻一 【住所又は居所】兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目8番地の14 【発明者】 【氏名】浦本 鴻一 【住所又は居所】兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目8番地の14 【要約】 (修正有) 【課題】引力と浮力を利用して浮体を上下運動させることにより、エネルギ−を取り出すこと。 【解決手段】浮体3にペダル5が、浮体4にペダル6に連結されており、ポンプ13によって容器2から容器1に水が移されると浮体3が浮き上がりペダル5が押し上げられる、其の時、浮体4が容器の水が抜け下降してペダル6を引き下げる、この運動が頂点に達するとポンプ12によって容器1から容器2に水が移されると浮体4が浮き上がり、ペダル6が押し上げられる。其の時、浮体3は容器1の水が抜けて下降しペダル5を引き下げる。この様にしてその上下を繰り返しながらペダルを回転させて発電装置9を駆動する。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 船の沈んでいる部分の体積を没水体積と言い、容器内に浮体を配置し、それを上から発電機の負荷を掛けたまま、容器内に流体を注入することで没水体積にし、その没水体積のまま更に流体を注入又は排出することで浮体を上下させ、浮体の浮揚変化によって発電する方法。 【請求項2】 (請求項1)に記した方法であって、浮体は立方体形状であり、容器も浮体と同型で少し大きい立方体形状であって、容器は2つで一組とし、隣り合わせに配置されており、ポンプは容器間で流体を移し替えることで浮体を上下さす方法。ここで、ポンプは浮体を上下させる距離分だけ流体を移し替える能力を有する。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は脱炭素化が求められる中で、自然エネルギ−の発電源が不足している問題に対処するものである。本発明者は、引力と浮力を利用して浮体を上下運動させることにより、エネルギ−を取り出すことが出来ると考えた。しかし、其のエネルギ−の取りだし方に工夫が必要である。そこで、本発明者は二組の容器を用意し、容器の中に没水体積の浮体を浮かべ、それを上下運動させることにより、自転車のペダルのように圧力をかけて回転させることで、エネルギ−を取り出すことが出来るという発明をなした。 【背景技術】 【0002】 没水体積とは船の水に浸かっている部分の体積です。其の没水体積の浮力を利用してエネルギ−取ろうとして、没水体積の浮体を入れた容器2組用意し、その容器の水を交互にポンプで移し替えて、浮体を上下さして、その浮力で自転車のペダルを回しその回転で発電機を回せば電気が取れます。 〔没水体積の性質〕 【0003】 没水体積は同じ1万m3でも高さ1万mの底辺1m2でも、100mの高さの底辺100m2でも、1mの高さ、底辺1万m2でも没水体積は1万m3です。これ没水体積と同じ立体で少し大きい容器に中で浮かせば、1万トンの浮力がつきます。この容器に水を注ぐと浮き上がりますがその圧力が10,000トン×1,000=10,000,000kg×9.8m/s2=98,000,000Nとなります。 1万トンの浮く圧力はどんな形状を取ろうともどれも同じです。 没水体積の浮体の上昇と水量の関係 【0004】 容器の中に容器と同じ立体で少し小さい没水体積の浮体を浮かせた場合、それを上昇させるために必要な水の量は、例えば没水体積1万トンの場合は容器の高さ10,003m底辺1.03m2の容器に浮体を水入れて3m浮かせる場合、必要な水の量は(3m×1.03m2)+(10,000m×0.03m2)=3.09+300=303.9m3です。しかし容器が高さ103m、底辺100.03m2容器に、高さ100m底辺、100m2の浮体をいれて3m浮せる場合は必要な水の量は(3m×100.03m2)+(100m×0.03m2)=300.09+3=303.09m3と同じです。又、容器の高さ4m、底辺10,000.03m2の容器に1mの高さで底辺10,000.03m2の場合の浮体入れて3m浮かせる場合は必要水の量は(3m×10,000m2)+(1m×0.03m2)=.30,000+0.03=30,000.03m3となり、高さが低いと極端に必要な水の量が大きくなります。これが2m上昇させる必要な水の量や1m上昇される必要な水の量も同様に計算できます。 これは容器と浮体の隙間がある場合で隙間が無かった場合は1万mの高さの場合は3m×1m2=3m3で、100mの高さの場合は3m×100m2=300m3で、1mの高さの場合は3m×10,000m2=30,000m3と必要な水の量は変わります。この違いは勿論隙間の問題で起こることなのですが、張排水時の吐水口など隙間を作らざるをえないので、一概に高ければいいという問題でもなさそうです。それに建築できるかの問題があり高ければいいというものではないが高いほど必要な水の量は少なくて済みそうです。そこで高さの取り方は没水体積を立方体に作るのが良いのではと思い、長さ巾高さを同じ作りにすれば隙間と底の水の量が釣り合ってくると考えました。 〔1万m3の没水体積で取れるエネルギ量〕 【0005】 これ自転車こぎ方式のペダル回す方法でやると、ペダルのリ−チを幾らにするかで、どれだけ浮かすかが決まり、それによって取れるエネルギ−量も変わってきます。10,000,000kgの圧力で自転車の腕1.5mとしリーチは3m、これを3分間に1回回転することにすれば。 角速度は1/3×2×3.14÷60=0.03488rad/sとなります。 それで自転車の腕1mの場合リーチ2mの場合も.腕0.5mの場合、リーチ1.0mの場合でも、仮に皆3分間に1回転すると角速度は皆0.03488rad/sとなります。 これをワット数算出する式で計算するとワット数=圧力(kg)×腕の長さ×角速度であるからリーチ3mの場合は10,000,000kg×9.8m/s2×3×0.03488rad/s=10,254,720w発電できることになります。これは1秒間ですから1時間では10,254kwhの発電となります。 リーチ2mの場合は10,000,000kg×9.8m/s2×2×0.03488rad/s=6,836,480w=6,863kwhとなります。 リーチ1mの場合は10,000,000kg×9.8m/s2×1×0.03488rad/s=3,418,240w=3,418kwhこれは浮体を3m、と2m、と1m浮かせて取れる発電量です。 だが浮体が沈む時、浮体に重量が無いため、二つをペアにして作り、片方が沈む時、ペアのもう一方が浮き、それをカバ−しなければならない。 『(0005)の場合に必要な水の量』 【0006】 3m浮揚さす場合の高さ1万mの場合 1回浮揚するために必要な水の量は303.09m3必要ですから3分間で1回転であるから1時間に60÷3=20×303.09m3=1時間に6,061.8m3の水を移動させなければならない。 3m浮揚さす場合の高さ100mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は303.09m3必要ですから3分間で1回転であるから1時間に60÷3=20×303.09m3=1時間に6,061.8m3の水を移動させねばならない。 3m浮揚さす場合 高さ1mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は30,000.123必要ですから、3分間に1回転ですから1時間で60÷3=20×30,000.12=1時間600,002.4m3必要です。 又2m浮揚さす場合 高さ1万mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は302.06m3ですから、3分間で1回転であるから60÷3=20×302.06=1時間6041.2m3必要です。 2m浮揚さす場合 高さ100mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は203.06m3ですから、3分間で1回転であるから60÷3=20×203.06.=1時間4061.2m3必要です。 2m浮揚さす場合 高さ1mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は20,000.03m3ですから、3分間で1回転であるから60÷3=20×20,000=1時間400,000.6m3必要です。 又1m浮揚さす場合 高さ1万mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は301.03m3ですから、3分間で1回転であるから1時間に60÷3=20×301.03=1時間6020.6m3必要です。 1m浮揚さす場合 高さ100mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は103.03m3ですから、3分間で1回転であるから1時間に60÷3=20×103.03=1時間2060.6m3必要です。 1m浮揚さす場合 高さ1mの場合 1回浮揚さすために必要な水の量は10,000.03m3ですから、3分間で1回転であるから1時間に60÷3=20×10,000.03=1時間200,000.6m3です。 〔同じ没水体積で高さと浮揚距離の違いによる1時間の発電量と必要な水の量の表〕 【0007】 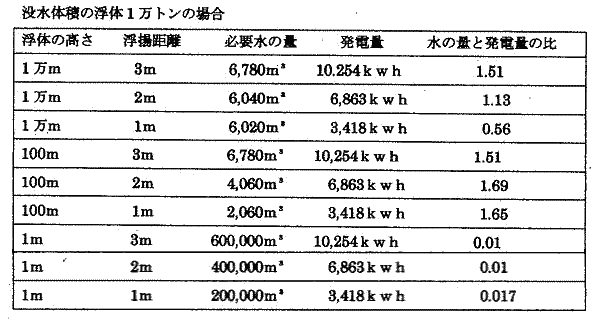 理論的には浮体の高さが高いほど浮かす水の量が少なくできるのだが、之から見ると没水体積の浮体と容器の隙間や、注入する水の流れを考えると一概に高い方が良いとは言えないようで、容積的に球に近い立方体で没水体積の浮体を作るのが最適なのではないかと思う、そうして浮揚の距離なのですが同じ没水体積で在れば必要な水の量と発電量の比は同じで、発電量同じにするなら移動距離を長くすれば使用する床面積をすくなくすることが出来る。 〔容器に没水体積の浮体を組み合わせたものを2つ作り一対とする〕 【0008】 浮力は上向きで、下降するときは浮体に重さが無く引力がかからないため、下降時は一対の別の浮体の上昇力を利用して上下に稼働さすため、2個一の組み合わせが必要で容器の中に没水体積の浮体を入れた物二つを組み合わせねばならない。尚2個を組み合わせるのは、一方が浮くとき一方を下降さす為、一方は水を抜き、その抜いた水をもう一方へ移し、そちらを浮かせるので1挙両得になる。 〔ポンプの消費電力〕 【0009】 寺田ポンプのセルプラポンプ150口径は吐出量3.2m3/min全揚程38m、消費電力37kwという性能を持っています。このポンプを使って1万m3の没水体積で100mの高さがある、浮体が天辺まで浮いて上の床のリミットスイッチに当たり、今まで隣の容器から吸って、この容器に注水して、これを浮上さしていた注水のポンプを止めると同時に、今の容器から今まで吸水していた方へ移し替えるべく反対にこちらから吸水して隣へ移す為には、反対のこちらから吸水して、ここより隣の容器の没水体積で3m低い位置の浮体へ注水し、その低い位置が反対に3m高くなり、汲みだす方は3m低くなりますが水面の位置は3mしか違わない為、揚程は3mでよく揚程3mとなります。1時間に6,780m3揚水するには6,780÷3.2÷60≒35.4台のポンプが必要です。1台当たりの消費電力は37kwhなので35.4台で1,310kwhとなります。しかしこれは反対側に注水する時も同じ数のポンプを使うという前提です。実際には片側を休ませるためポンプは倍にして半分ずつ交互に注水することもできます。 この場合、消費電力は同じ1,310kwで済みます。ただし、この計算は理想的な状況で行ったものであり、実際にはポンプの効率や配管の抵抗などを考慮する必要があります。 又、吐出口や、吐出量、全揚程と消費電力はポンプの設計によって変わります したがって、最適なポンプを選ぶためには、ポンプ製作所に相談して、条件の合った仕様を決めるのが最適です。 〔取れる電力〕 【0010】 1万m3の没水体積で高さ100m、揚程3mが2個1で取れる電力10,254kwhですから、ポンプの消費電力1,310kwh引けば8,944kwh取れることになります。仮に稼働率50%としても4,472kwhになります。 〔容器二つの間の移送時、揚程を短くしてポンプの負担を軽くする方法〕 【0011】 没水体積の浮体を浮かせた容器の水は常に没水体積を沈める高さで水面を維持します。だから没水体積の上面までは水があることとなり、その上面以下に給水口があれば吸い上げられますし、吐出口は容器の上面に取り付けねばならない、なぜなら浮体は浮いてくるので底に水溜める為には上から落とせばいいので下から注ぐのは圧力かけなければならず不利である。 又浮体の入った容器の水を空にするのは荷重かけないで浮体を低くするため最初だけで稼働しだしたら常にモ−タ−の荷重が掛り、底が容器の底に付、すぐ浮かせなければならず浮体浮かすためには、その時点で注入しなければ成らず、容器の水面は浮体が容器の水面で止まりそれ以上は下がらない。だからその水面より下に給水口があればいいので底から吸い上げる必要はない。 没水体積の浮体の上下運動の切り替え方法 【0012】 一つの容器の浮体が水位の上昇により浮上して頂点に足したら、浮体の頂店が上の天井に取り付けられているリミットスイッチに触れ、注水ポンプのモ−タ−の電源が切れます。その容器への注水は中止されると同時に、反対の容器のモ−タ−に切り替わり、反対の容器のポンプが動き始め、反対側の容器への注水が始まります。これを繰り返して、二つの容器内の浮体がお互い反対の上下を繰り返し、ペダルを回転させ発電機を回転させ続け、発電します。 もし荷重が少なく没水体積まで沈まなかった場合の対象法 【0013】 浮体は荷重に応じて沈みますが、荷重が少なくても浮体が頂点に達すればリミットスイッチが作動しポンプを使って調整します。リミットスイッチは浮体の頂転に設置されており、浮体が浮いて頂点に達すれば作動します、ポンプはリミットスイッチの接触で切り替えられ水を容器から容器へ移しながら浮力を調整します。この仕組みにより、発電機取り付け時から最盛期まで、浮体の没水体積を自動で調整することができます 【発明の概要】 【0014】 立方の容器の中に、それより少し小さい浮体を入れたものを2個用意し、1組にする。そのうち1つの容器に水を流し込み、浮体を浮かせる。浮体の力でペダルを押し上げ、発電機を回す、ペダルが頂点までくると、ポンプで水をもう1方の容器に移す。これにより、反対側の浮体が浮き上がり、反対側のペダルを押し上げる、同時に先のペダル押し上げた浮体は水が抜け下降し、ペダルを引き下ろす。このようにして、ペダルを回転させて発電する。 (0007)(0008)(0009)(0010)で説明したように浮体を高くすれば引力を強く受けられ浮力がましてこの方法で電力取ればポンプ消費量より発電量が多くなり電気が取れる。 【発明の効果】 【0015】 この発電装置は、引力と浮力を利用して、脱炭し炭素の排出量を減らすことが出来る。 【図面の簡単な説明】 【0016】 【図1】配置略図(正面図)モ−タ−への配線やポンプの配管や接続先の配置図です。 【図2】配置略図(平面図)上記でわかりにくいところをもっとわかりやすくした平面配置図です。 【図3】ポンプ用モ−タ−の切り替えスイッチの作動状況図 【図4】浮体稼働状況図 【発明を実施するための形態】 【0017】 この装置は符号1と2へ交互に水を移し替えて、符号3と4の浮体を交合に浮かし、その浮力を符号7と8のピストンへ伝え、そのピストンが符号5と6のペダルを押し上げシャフトを回し、符号9の発電機を回して発電してその発電機の電気の一部を符号11と12のモ−タ−を回して、符号13と14のポンプで符号1と2の容器に水移し替えて浮体を上下させ、その浮体の上下の浮力で発電する。其れで取れる電気の一部をポンプに回しても其れ以上電気が取れることを(0007)(0008)(0009)(0010)で説明しています。 【符号の説明】 (0018)(図1)(図2)(配置略図)の符号 符号1は左辺の符号3の浮体を入れる容器 符号2は右辺の符号4の浮体を入れる容器 符号3は左辺の符号1に入れる浮体 符号4は右辺の符号2に入れる浮体 符号5は浮体3の浮力を伝えて発電機を回すペダル 符号6は浮体4の浮力を伝えて発電機を回すペダル。 符号7は浮体3とペダル5を繋ぐピストン 符号8は浮体4とペダル6を繋ぐピストン 符号9は発電機 符号10は配電盤 符号11は左辺のポンプを稼働する電気モ−タ− 符号12は右辺のポンプを稼働する電気モ−タ− 符号13は左辺の容器より右辺の容器に水移すポンプ 符号14は右辺の容器より左辺の容器に水移すポンプ 符号15はペダル5と6によって回転を発電機に伝えるシャフト 符号16は発電機やポンプを設置するための床 符号17はポンプ13より容器2に水移送するパイプ 符号18はポンプ14より容器1に水移送するパイプ 符号19は容器1よりポンプ13により水くみ上げ符号17に送る吸水管 符号20は容器2よりポンプ14により水くみ上げ符号18に送る吸水管 符号21はポンプ13と14を稼働さすモ−タ−の稼動を切り替える切り替えスイッチ。 〔この切り替えは(図3)で説明する〕 符号22は10の配電盤よりモ−タ−11を繋ぐ配線 符号23は10の配電盤よりモ−タ−12を繋ぐ配線 符号24はモータ−11より切り替えスイッチ21を繋ぐ配線 符号25はモータ−12より切り替えスイッチ21を繋ぐ配線 符号26は配電盤10より切り替えスイッチ21を繋ぐ配線 この26より24へつなぐか25へつなぐかでモ−タ−の11と12が交合に稼働する。 符号27は発電機より配電盤に電気を送る配線。そこで調整して外部へ送電すると同時に容器の水を移すポンプを稼働さす、モ−タ−を稼働する。 符号28は外部への送電線 (図3)ポンプ用モ−タ−切り替えスイッチの符号 符号1は左辺の浮体3を入れる容器 符号2は右辺の浮体4を入れる容器 符号3は左辺の容器1に入れる浮体 符号4は右辺の容器2に入れる浮体 符号5は左辺のリミットスイッチ(浮体が上がりシーソ7の辺を突き上げ先端が9の電線端子に当たり11の配電盤につながっている20の配線とつながり12のモータ−が回り、14のポンプが稼働して18の給水管から16の移送管より2の容器に水が移る。 其の時シーソの上の重りが転がって右辺に移り、左辺のリミットスイッチが下がっても9電線端子にシーソの左辺が接触を続けて符号6が右辺を押し上げるまで配電盤との線は繋がり続ける。) 符号6は右辺のリミットスイッチ(浮体が上がりシーソ7の右辺を突き上げ、先端が10の電線端子に当たり11の配電盤につながっている20の配線とつながり13のモ−タ−が回り、15のポンプが稼働して19の給水管から17の移送管より1の容器に水が移る。 其の時シーソの上の重りが転がって左辺に移り、右辺のリミットスイッチが下がっても10電線端子にシーソの右辺が接触を続けて符号5が左辺を押し上げるまで配電盤との線は繋がり続ける。) 符号7はシーソ(これは配線端子9と10への切り替えスイッチである。) 符号8は重り、(これはリミットスイッチが電線端子9や10へ接点はつなげるがすぐに下がり符号9や10の接触を続けられない為、重りでそれをできる様シーソの状態を維持するための物である) 符号9は左辺の電線端子(配線22によってモ−タ−12につながっている) 符号10は右辺の電線端子(配線23によってモータ−13につながっている) 符号11は配電盤 符号12はポンプ14を稼働するモ−タ− 符号13はポンプ15を稼働するモータ− 符号14は左辺のポンプ(容器1より吸水管18で水を吸い上げ移送管16で容器2へ水を移送するポンプ) 符号15は右辺のポンプ(容器2より吸水管19で水を吸い上げ移送管17で容器1へ水を移送するポンプ) 符号16は符号14のポンプより容器2へ送る移送管 符号17は符号15のポンプより容器1へ送る移送管 符号18は符号1の容器よりポンプ14が吸い込む吸水管 符号19は符号2の容器よりポンプ15で吸い込む吸水管 符号20は符号11の配電盤よりシーソに繋ぐ配線 符号21は符号11の配電盤よりポンプ14を稼働するモ−タ−12とポンプ15を稼働するモ−タ−13を繋ぐ配線 符号22はモータ−12と端子9を繋ぐ配線 符号23はモータ−13と端子10を繋ぐ配線 符号24はシーソ7の支柱 (図4)浮体稼動状況図の符号 符号1は浮体3を入れる容器 符号2は浮体4を入れる容器 符号3は容器1に入る浮体 符号4は容器2に入る浮体 符号5は浮体3に繋がるペダル 符号6は浮体4に繋がるペダル 符号7は浮体3とペダル5を繋ぐピストン 符号8は浮体4とペダル6を繋ぐピストン 符号9は発電機 符号10は符号12のポンプを稼働するモ−タ− 符号11は符号13のポンプを稼働するモ−タ− 符号12は容器1から容器2へ水を移送するポンプ 符号13は容器2から容器1へ水を移送するポンプ 符号14はポンプ稼動用モータ−切り替えスイッチ 符号15は発電機を回すシャフト 符号は水面を表す 図Aは左辺の容器の浮体が頂点に達し符号14のポンプ稼働用のモータ−切り返へスイッチのリミットスイッチがポンプ切り替えスイッチ押してポンプ12の稼働を開始する、それにより容器1の水が容器2に移り始め、段々と浮体4が浮いてきて浮体3が下がる、そうして図Bにいたる。浮体3と浮体4の水面が同じ状態になりこれからさらに浮体4が上昇し、浮体3が下がり図Cの状態となり左辺の浮体4が頂点に達しリミットスイッチが符号14のポンプ稼働切り替へスイッチ押して12の反対の11のモ−タ−が回り13のポンプを稼働させ容器2より容器1に水を送り出し浮体3が浮き始め浮体4が沈み始め図Dへ移る。その後もポンプ13の稼動は続けられ図Aの3状態になり其れが繰り替えされ浮体の上限運動が継続されることによりその運動がピストンによりペダルに伝わりシャフトを回して発電機が回り発電する。 産業上の利用可能性 【0019】 引力は世界中どこでも存在するエネルギ−であり、それを利用して水に浮力を発生させ、力を与えたり、除去したりしながら浮体を上下さして、其の動力で発電することが出来る ここで強調したいのは先に(0007)(0008)(0009)(0010)で述べたように、それに必要なポンプ消費電力よりその発電が勝るので電気が取れる。更にその電気を使って、水素も生成することが出来る。 |
【図1】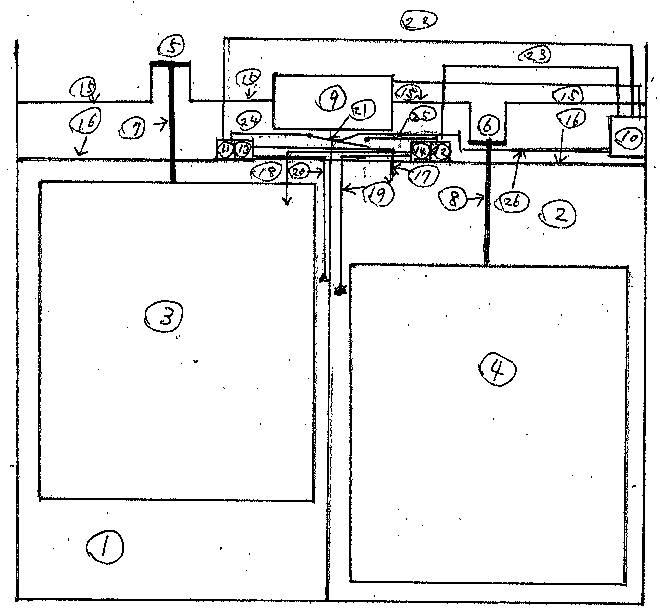 |
【図2】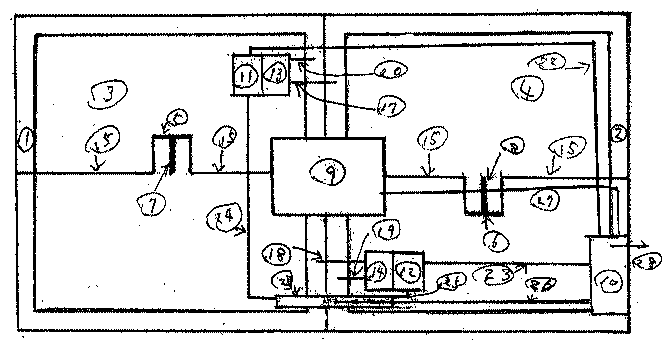 |
【図3】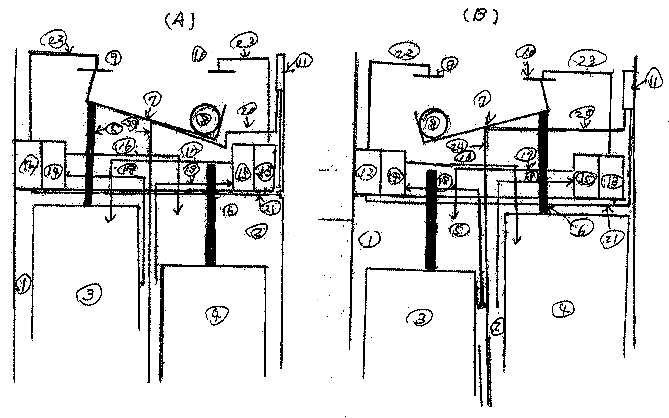 |
【図4】 |
| ページtop へ |