| 閉じる |
| 【発明の名称】海洋のセキュリティーと可視化システム 【出願人】 【識別番号】522196711 【氏名又は名称】有村 國孝 【住所又は居所】神奈川県茅ヶ崎市下寺尾2286-12 【発明者】 【氏名】有村 國孝 【住所又は居所】神奈川県茅ヶ崎市下寺尾2286-12 【要約】 (修正有) 【課題】海上、海中、更に海底のセンシングを可能にし、海の中の事象もより把握する新しい海洋セキュリティーと情報収集システム及びセンサシステムを提供する。 【解決手段】センサシステムを用いて、海上、海中又は海底からの信号を集受する方法は情報量の多い海底ケーブルを守るためにセンサを設けることと、更に海洋の種々の情報をセンサにより探知し、海中の様子が可視化することと、更に海洋と陸上の夫々のリアクションや交流による陸上、海上の安全を守るために海中にセンサを置き光ケーブルで情報を常に得られるようにすることと、を含む。 【選択図】図5 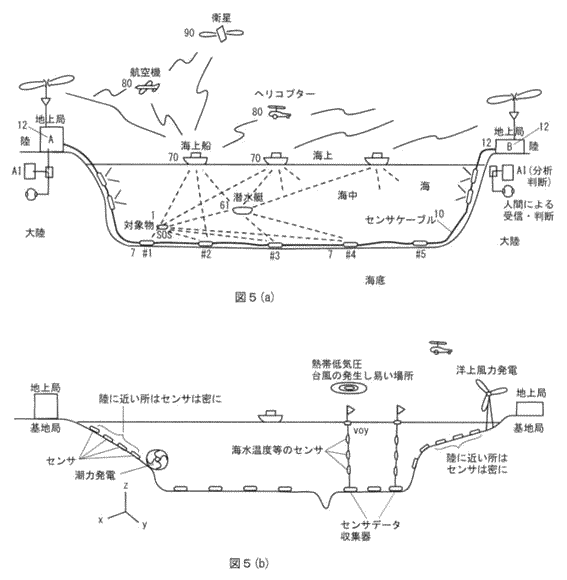 【特許請求の範囲】 【請求項1】 海底ケーブルを海中での通信にも利用を可能にするとともに、海底ケーブルの事故を防止するシステムを構築することを特徴とするセンサ付セキュリティーと海洋情報収集システム 【請求項2】 適切な間隔を置いて配設置された多数の音響センサ、振動センサ、光センサ、磁気センサ、電波センサ、温度センサ、海流センサ、汚染度センサのうち一つあるいはそのうちの何れでも供えたセンサ装置から得られる信号をアナログ信号の場合はA/D変換をなし、Digital信号の場合は適当な変調信号とし光を変調し、光ファイバーケーブルで信号を伝送し、当該波の発信源を特定ないしは追跡することを特徴とする、振動波、音波による海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項3】 センサ付当該ケーブルを海底ケーブルと並行して敷設することを特徴とする、救難信号、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流、汚染度何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項4】 センサ付当該ケーブルを海底ケーブルと中継器の所で一体化し、海底ケーブルと共に敷設可能としたことを特徴とする、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、汚染度、海流何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項5】 センサ付当該ケーブルを主海底ケーブルの分岐ケーブルとなし、得られた信号は主海底ケーブルの専用光ファイバーまたはMultiplexerによって回線の空きチャンネルに重畳させ伝送線としては一本化することを特徴とする、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流、汚染度何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項6】 音響センサから得られた信号と振動センサや当該各種センサから得られた信号を対比し、各センサから得られた信号を分析し、信号を識別し、遭難者を含む対象物を特定、選別、判別、追跡することを特徴とする、振動波、音波、光、電波何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項7】 音響センサ、振動センサ、光センサ、磁気センサ、電波センサ、温度センサ、海流センサ、汚染度センサ何れかにでもよるセンサから得られる信号をAIやコンピュータによって分析し、必要な信号のみを抽出することを特徴とする、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流、汚染度何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項8】 音響センサ、振動センサおよび当該各種センサを備えた光ケーブルシステムと、無人水中潜水艇とを組み合わせて、海底と海中のTargetを捕捉することを特徴とする、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流、汚染度何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項9】 音響センサ、振動センサおよび当該各種センサを備えた光ケーブルシステムと、無人潜水艇と、海上船舶とを備えたセンサや送受信装置により、海中、海底、海上のネットワークを構築することを特徴とする、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流、汚染度、何れかによる海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項10】 音響センサ、振動センサ、光信号センサ、音波探知機や映像から得られた総合的な情報と、振動波、音波、光、磁気、電波、温度、海流探知装置、汚染度計測装置、センサ装置による海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項11】 光伝送レーザ、LED、100m〜200mの範囲を、電波、数m〜10mの範囲を、音波は周波数によって異なるが約50km程度、磁気、温度、海流、汚染度をセンシングすることを特徴とする、海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項12】 単に陸上間の間の通信を行う目的で海中、海底では横断の目的で横たわっている海底ケーブルを活かし、海中においても、海中の各種の情報を取得、海底ケーブルを守るためのセンシング情報を伝送することを可能にした海底ケーブルおよびセンサーケーブルによる海洋セキュリティーと総合的情報収集システム 【請求項13】 海中の音波、振動波、光、電波信号を受信する受信装置が海中に点在し、これを接続する光ケーブルによる伝送路を介して発信源の信号をDigital変換したのち、光をPSK、ASK、FSK、TDM時分割変調を行い、光ケーブルで伝送し基地局あるいはステーションでDecodeし、Targetを特定することを特徴とする海洋セキュリティーと情報システム 【請求項14】 ケーブルに沿って敷設された線状のセンサ列により、Targetを追跡することを特徴とする海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項15】 海中の複数本のセンサケーブルとセンサを面状に配列させ、この近くを通過するTargetを追跡できるようにすることを特徴とする海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項16】 水温、CO2、CH4、O2、放射能を検出するセンサによって得られる海中の各Dataを海中に海底ケーブルに沿って備えたセンサケーブルや海底ケーブルによりデータを収得することを特徴とする海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項17】 無人潜水艇において、船体の内部の圧力と外部の海水の圧力とが常にほぼ同一となるように水や液体を船内に蓄え圧力調整弁を設け機器はほぼ球体に収納し、高水圧から保護する構造を特徴とする海洋セキュリティーと情報収集システム 【請求項18】 センサケーブルあるいは海底ケーブルを伝送路として、センサが平面状に配列されたり、立体状に配列され、これをセンサケーブルで結び、伝送し、基地局に連絡することにより、海中の情報が立体的に得ることができ、海洋の現象がより明確とすることができるようにするセキュリティーとセンサシステム 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 海の中の通信の方式に音波を使ったもの、レーザや光を使ったもの等がある。音波を使ったものは超音波によるものがあるが距離が限られ音の伝達スピードや周波数が電波に比べ低いため情報量も少ない。 また、地球の7割が海と云う広さをカバーする通信は今だ殆んどない。 折角敷設された海底ケーブルが事故や故意によって切断される予想もある。これも防止しなければならない。 光ファイバーケーブルそのものとセンサは確かに安上がりとなりますが、機械的振動とか、曲げとか、周期的反射とかを利用するので、不安定要素も発生し易いし、ノイズともなるし、長距離の安定したセンシングは無理である。従って、主ケーブルとしては使い難い。一部のセンサとしては使える場合もある。 本発明の発信源からのID信号も受信できないし、はたして、キャピテーション、スクリュー音、環境情報のCO2、CH4、O2、P、温度、放射能、汚染等のセンシングが可能かと云うと無理であり、上記の事象に対するセンシングを行うことが必要であり、光ケーブルを守るとともに上記のセンシングも可能とする。 従って光ケーブルによるセンシングのみでなく多くの他の情報も得ることが出来るとともに、本発明の主題の一つである従来の光ケーブルを守るばかりでなく、人命救助等、更にこれを利用して海中の情報も得ることにより、海中の多くの情報を得るとともに海中を可視化できるメリットが得られる。 上記の方法により、海底ケーブルの防衛が可能となるばかりでなく、海底ケーブルの付加価値が増々増大する。 陸上と同様可視化することが出来るとよい。 【背景技術】 【0002】 大陸間の通信の99%は海底ケーブルで行われている重要な通信網である。 ケーブルの本体は石英ガラスで出来た細線の中を光信号がパルス信号となって伝送され、約90km毎に減衰を補う中継器(増幅器)が設置されている。情報量が増すに従って大容量化が進んでいる。現在でも約400本のケーブルが大陸間に敷設されており、このケーブルの敷設には莫大な費用が掛かっている。一番深い所で8000mの深海もケーブルが連続して敷設されているので、断線や事故にあった時は修復しなければならないが、この個所を突き止めるにも、また防止するにも、引き上げ修復するにも見えない海の中である。 近年、海難事故が頻発し、折角敷設した海底ケーブルの保護、領海の侵入や侵略等が起こっている。海中や深海等はまだまだ未知の所が多い。陸上の汚染は海につながり、また海の環境が陸上に大きく影響を与える。これを改善、明確にすることも重要である。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 (別紙1)沖電気の中の参考文献とNECのレポート等 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 本発明の海底ケーブルの保護によって大陸間および海洋横断の通信すなわち国際間の通信の殆どが安全に行われることになるばかりでなく、ケーブルを守り、更に海中の様子も知ることができ、且つ、今迄不明であった広い海中や海底の様子がかなり明確にすることが出来るようになる。 人類が地球を離れ、月や火星に行くことも計画しているが、地球の海中に沈んだ船舶、航空機、ヘリ、また潜水艦等、見つけられない状態であり、海は未開な状態であった。海にすむ動物、植物の行動もよく分っていない。 温暖化等により台風は益々大きくなり、汚染により赤潮の問題、プラスチックごみの問題等、陸地と海洋は結びついている。 日常生活の生命線とも云える情報ネットワークの海底ケーブルを守ることができる。 本発明によって得られるDataや今後更に敷設される海底ケーブルや無人潜水艇により多くの情報が得られるようになる。海底の情報が得られるに従って多くの資源の開発も促進されることになる。 以上のように単に海中、海上の情報のみならず陸上生活の安全や自然の循環系の情報にも役立つ。 【課題を解決するための手段】 【0005】 先発明のID信号を発生させる振動数や音響デバイスから発するID信号を受信する海上の船、無人・有人潜水艇により、音響発信デバイスの位置を探り当てることを説明した。 膨大な広さの海の中で発信信号を発見するのは大変である。 然るに海底には海底ケーブルが敷設されているし、今後も敷設される。現在でも400本以上の約120万キロメートルのケーブル網が構築されている。将来的には、人口の多い発展途上国を含め更に需要が広がり、早々大容量化を要求され多くの伸び率が予想される。 また、従来のケーブルを利用するのが難しい場合は、このケーブルに沿って新しくケーブルまたはセンサーケーブルを敷設することにより目的を達するようにする。今後新しく敷設する所、更新する所には海底情報用当該ケーブルを敷設すればよい。 更に、海底ケーブルが切られる事故が発生の折、この原因やどの場所で何によってか等の原因を突き止め防止する必要がある。この目的のため、船舶等のスクリュー音、錨や漁網等の引きずる音、通った船舶等のスクリュー音、エンジン音や回転音、キャピテーション音等を分析、特定できれば被加害者を特定も出来るし、夫々の中継器や分岐ケーブルに取り付けられた夫々のセンサからの情報を追跡することにより、船舶、潜水艇、ステルス移動物、動物、等の特定や移行を追跡することが出来る。未然に防止も可能となる。 実施例として、中継器の増幅器や中継器やセンサの位置IDとともにケーブルを伝って監視ステーションに連絡するよう構成することにより、単に陸上の通信(や電力送電)のみでなく、センサや送受信設備により海中の情報も多数集めることができ、且つ、海の安全、交通安全、空の安全等を守る地球全体の監視機能を設置することができるようになる。また、低気圧や台風、ハリケーン等の海の環境を知ることにより陸上の生活の安全や自然の脅威を減らすことができる。 【発明の効果】 【0006】 1.海底に敷設されているケーブル、センサ等を利用して種々の情報を送信、受信できる。 2.まず、ケーブルの位置を海の中で正確に知るようになる。 3.ケーブルが切られないように警戒できるようになる。 4.何によってケーブルが切られたか知ることができる。 5.中継器のようにケーブルが途切れる場所、あるいは別途取り付けられる可能性のある部分を利用して種々のセンサを取り付け海中の様子を知ることができる。 6.中継器に分岐を設け、ここに振動音波、映像(カメラ)各種センサを取り付けることができる。勿論、独立したケーブルとセンサを用い、所々に中継器を置くこともできる。 7.ケーブル位置や中継器位置に所在を示すID信号を取り付け、水中あるいは水上にある船舶や潜水艇により複数の受信を行うか指向性アンテナや水中レーダを用いて方向を探知できるようになる。これにより?が可能となる。 8.単に大陸や地上を結ぶ通信ケーブルとして利用するのではなく、センサや送受信装置により海の中の情報を探知したり伝えたりする発信・受信拠点として利用できるようになる。 9.何らかの理由で海中で発生した活動物(遭難者)との交信が保てるように各センサ信号を探知し、追従するように出来る。 10.海中の動植物、鉱物との直接・間接の通信を含め発見、追跡ができるようになる。 11.海底トラフの移動を検知することもできる。 12.地震予知のための異常振動を検知して、その発生地点、予測される大きさを報知することができる。既に地震計が設置され、このデータをケーブルを介して得ている場合には、更に海中のデータ収集も行えるようにできる。 13.更に地球環境に影響を及ぼす海水温、CO2、CH4、O2、海流、汚染および水圧と関係する深さ等のデータを同時に取得し、海水の状態をリアルタイムで取得できるので、海中、海上、陸上で起こる様々な現象を予測することができる。 台風や降雨、海の汚染等、陸上と密接に関係し、今迄、とくに深海等、見過ごされてきた海洋の変化と陸上の影響について新たな情報源として利用できる。 等、当該発明の技術により多数の応用が可能となる等、多くの発展的応用が可能となり海の安全や解明果ては陸上の生活にもに役立つ。 【図面の簡単な説明】 【0007】 【図1】図1は、従来の海底ケーブルの敷設状況を示す図である。 【図2】図2は、従来の海底ケーブルの構成を示す。 【図3】図3は、ケーブルの中継器から分岐を出して海底の様子を探るセンサを取り付けた場合を示す。 【図4】図4は、海底ケーブルに沿って別途センサケーブルを敷設した場合を示す。 【図5】図5は、海中の移動物、人間、船、潜水艇、飛行体、動物等、から発せられたID信号を追って航跡等を知るため本発明のセンサシステムを用いて、海上、海中、海底からの信号を集受する方法を示す。 【図6】図6は、中継器の近くに取り付けたセンサ付振動子、音波、電波、光等の信号を使って、IDのみでなく種々の信号をセンシングする方法を示す。 【図7】図7は、探索用無人潜水艇の凡その構造と、水圧に耐える構造を示す。 【図8】図8は、深海の水圧の高い所でも動作する音波振動センサの構造や逆に音波振動を電気に変える方法の実施例を示す。 【図9】図9は、特定の信号の位置を特定するため夫々のセンサからの信号を受信し、受信信号の到達時間を分析すると発信位置が分かりケーブルを介して信号を伝送することを示す。 【図10】図10は、targetがどの位置にあるか複数のセンサからの信号で読み取ることができることを示す。移動するtargetも捕捉できる。また網目状のセンサにすることにより面で位置を捕捉できる。 【図11】図11は、センサにより受信された信号音や振動音等をAIにより自動的に分析するか人間によって判定する内容の説明図である。 【図12】図12は、センサ信号を伝送する場合、センサ信号を単独で伝送するか、周波数多重で伝送するか、別途ケーブルを敷設するかどちらでも出来ることを示す。 【発明を実施するための形態】 【0008】 本発明を図に従って説明する。 【0009】 図1は本発明の振動波、音波による海洋情報収集方式に関して、既に海中に敷設された通信網である別の目的の海底ケーブルの従来の実施例の説明のための図である。 同図のようにケーブルは大陸間の通信に利用されているのみで海底は単に横断のために横たわっているのみである。広い海の中で何処で切られるかも分からない不安な状態であり、また海中では貴重な存在でもあるにも拘らず、海中の役には立っていない。海底ケーブルのみでなく、現在敷設されている海底のトラフやパイプ電力ケーブル等も同様である。 【0010】 図2はケーブルの中継器を利用して途中で分岐する従来の方式を示す。同方式も海中は素通りで陸上通信のみに利用されている方式である。 【0011】 図3は本発明の海洋の通信のための中継器を分岐に用いる場合を示す。 図3(a)は本体ケーブルの中にセンサ信号が重畳されて、中継器の部分にセンサ部を設置し、中継器を共有する場合を示す。この方式は大陸間の重要な通信の回路とマルチプレクサ部を複雑にし、また大陸間通信と水中センサ部の責任の分担も複雑になるので最初は図3(b)のように中継器の一部は利用しても基本的に別々の2本のケーブルによって構成した方がよい場合もある。 図3(c)は中継器でセンサケーブルを分岐する場合の外装の実施例を示している。2本のケーブルは並行して敷設され、またドラムあるいはローラに巻かれるので敷設も容易である。 中継器の所で一体化するが、本線に影響を与えないように分離して構成している。 図3(d)は主ケーブルと分岐ケーブルが中継器を利用して分岐する場合の外装の実施例の断面図を示す。 【0012】 図4は海底ケーブルとセンサ信号や情報を伝送する情報ケーブルと主となる海底ケーブルを分けて並行して敷設する場合を示す。 センシングする対象物は何番目のセンサに近いかをセンシングすることによって対象物の位置を特定できる。特定の信号の位置を特定するため夫々のセンサからの信号を受信し、受信信号の到達時間を分析すると発信位置が分かりケーブルを介して信号を伝送する。 【0013】 図5(a)は地上局で対象物の信号を受信した場合、地上局A側でもB側でも受信可能としていた場合、どのセンサに信号が入って来たか?また、その時間は、強さは等、を自動的にAIを用いて判別する仕組みを示している。 一方、信号の受信や警報を直接監視員が聞けるようにすることも出来る。 人間が聞く場合にはDigital信号を更にAnalogue信号に変換して聞くことが出来る。 実際には多数のセンサや中継器があるのだが、紙面では説明のため、仮に5個の場合を表示している。対象物が一番近いのは#1のセンサと#2のセンサである。#3、#4のセンサには遅れて信号が到達するのでこの時間差によって海中の音速からの到達時間と#1、#2、#3、#4からの信号の到達時間や位相等によって対象物のIDや種類、状態、位置等を知ることが出来る。 図5(b)は、センサ並びに中継器は必要に応じて分配設置すればよいことを示している。 例えば、陸に近い所ではレジャー等、人間の活動が多く、それだけ情報が蜜となる場所である。従ってセンサも多く配置され、その分減衰や反射が発生し易くなり中継器も等間隔に設置と云う訳には行かなくなる。 また、台風や低気圧等の発生する熱帯、亜熱帯域には海水温を水深の層に分けて計測する必要もあるため海底からセンサケーブルを介して水温を測定し、水温上昇と蒸発、上昇気流の発生のメカニズムを常時計れるようにし、地上の台風の予測や被害を最少にするようにする。 CO2、CH4、等の温室効果ガスによる温度上昇は分かっていても正確な層の海水温等はつかめていないし、海流による影響もつかめていない。できるだけ多くの情報が得られるようにする目的である。図9を含めて、立体的に情報を集受することができる。 【0014】 図6(a)は、上空の衛星、海上の船、海中の潜水艇、海底のセンサは光ケーブルによる海のネットワークを組み、例えば航空機が事故に遭い沈んだ場合、人が海難事故に遭い沈んだ場合や潜水艦等の動向や通信を探知したり連絡したりするシステム例を示す。 現在、船が沈んだ場合でも沈船の場所、搭乗者等は見付からないままである。飛行機事故、ヘリコプター事故においても、陸にいて津波にさらわれた人も不明であり、敵と見なされる潜水艦も哨戒機で追跡するのみであるが、海中、海底、海上、上空のネットワークにより追跡が可能となる。 海底に敷設されたセンサ付光ケーブルにより、陸上の基地に信号が送られ音波の信号がDigitalに変換され更に光変調され基地局で受信することが出来る。図のA点基地局とB点基地局両方で受信可能であるが、どちらを選んでもよい。 図6(b)は、地上のセルラーステーションのように、100m〜200m置きに、光、電波、音波のステーションを設置し、重要なルートを保護、監視する場合を示す。レーザや高出力の電波を用いた場合、精々100m〜200mが限界と考えられるが、光や電波の場合、情報量が多く採取でき、正確な情報が得られるので重要なルートには用いることが出来る。 重要監視の目的は、海底ケーブルの切断防止用、不審な船舶や動物等の監視、貴重な海中生物の監視、トラフの移動・変動・亀裂、海底火山等の監視、船舶の定期航路の事故防止、発生に関する情報収集等の目的である。 【0015】 図7(a)は、無人潜水艇の主な機関の配置と断面図である。有人の場合、船体の中は空気であるため水圧によって船体が破壊される可能性がある。 然し、本発明では無人の潜水艇であるため船体内部は空気を充たさなくてよい、代わりに純水または水を充たし深部の圧力にバランスが取れるように圧力調整弁を用いて常に外と中の圧力を同一にし、圧力でつぶされないようにする。 船体前方に発信信号、追尾用のアンテナセンサを配備する。音波デバイスからの信号を受信する目的のアンテナで、??図7(e)のように受信センサが中心にあり、左右にどちらが信号が強いかとか位相等や到来波の進みか遅れか等により右か左からの信号が到来したかを判別することが出来る。 上下の3,4のセンサアンテナについても到達時間の遅れ等によって信号がどちら側から到来したかの判断ができる。 従って、主受信アンテナのみでなく、左右上下のアンテナから得られる信号の大きさや位相によってどの方向から信号が来ているか判断ができ、到来方向に向かって潜水艇の舵を切って行けば発信源を発見できる。 ある程度近づけば音波のみならず電波や光による伝送も可能となる。 上部の通信用アンテナは船艇が海上に浮上した時に、他の船や上空の航空機やヘリコプター、ドローン、陸上の通信施設と交信をするためのアンテナである。 また、船舶内部の圧力と海の何れの時の圧力と同一とするため弁または圧力調整(ピストン)を設けて深海でも船体が破壊されないようにしている。 潜水艇に仕込まれたセンサ類、通信器、制御器等の機器は深海の圧力に耐えるように球の中に収納している。また電力を得るためのバッテリーや燃料も球体の中に納められている。 更に艇を動かすモータやエンジンも球体に納められ深海に潜行した場合でも破壊されない。船艇の一番後方にはプロペラが取り付けられ船艇を推進させる。方向追尾については方向舵や羽根を操作し追尾する。 図7(d)には球体が四方から均等に押し付けられ、この力は球の表面に分散されることを示す。一般に球表面のVectorはrdθとrsinθdφに分けられ均等に保持され破壊され難い。 パラボラ面の基点部に取り付けられている振動子あるいは集音装置である。他の小形集音器1,2,3,4についても同様のものを用いてもよい。 夫々の集音器に到達する音の強さや位相によって方向が分かり、潜水艇の舵取りを行い発信源に到達できる。 【0016】 図8は、腰のベルトに送信源を付けた場合と、腕時計形の場合の送信源の実施例を示す。 図8(a)は、音の信号あるいは色々な振動音をダイアフラムD等の振動で動け、このダイアフラムの振動よる磁石によって構成されているとその周囲に固定されたコイルには誘起電圧が発生し、上下運動に従って電圧や電流は振動に応じた発電を行い信号を生み出すことが出来る。発信源の場合には電流の変化によりダイヤフラムが動作し音波を生む。 コイルの方は箱内に備えられており海水に浸かることはない。 振動板Dは膜面を介して海中とは遮断されており、海の付着物とかが付着することはない。 図8(b)は、水晶振動子、チタン酸バリウム等の発電素子の場合、電極の振動によって電圧が得られる。電圧を加えると歪が生ずるので振動子による電圧発生と電気振動により機械的振動やコード化された音波が得られる。 図8(c)は、振動版を送受信に用いる場合を、図8(d)は、送信用振動版と受信用振動版に分けて用いる場合を示す。 発振装置として用いる場合には体に装着するため小形で大きな振幅の出力を作らなければならない。 何れの発信装置においても時間を定めて、例えば午前9:00、正午12:00、午後3:00(15:00)とか定めて定刻に信号を送るように定めておくとこの時間に待機することが出来る。 事故が起きた瞬間に水に浸かった段階で自動的に電源が起動され信号がまず発信されるようにする。 それも10分程度連続して発信して、その後は間欠的に発信するように定めておくことにより早い発見とともに長期的にも使用できバッテリーの電圧が持続することが望ましい。 図8(f)は、潜水艇の先端には振動が伝わり易く且つ海水と内部の淡水を分けるための振動膜を張り振動がアンテナに伝わり易くする方法を示している。シリコンゴムのような膜面で構成するとよい。 先に述べたように、外部の海水は深くなれば水圧が大きくなるため破壊されないように外部の海水の圧力と内部の淡水の圧力が均等になるように可変弁が取り付けられている。 【0017】 図9は、targetからの発信源となる信号をセンサが受信し、この信号を光信号に変えて光ケーブルで伝送し、基地局で信号の判別や他への伝達を行う場合のシステム図を示す。 図9(a)は、Targetが備える発信源であって、定められた条件によって電源が入り、一定の間隔や時間でIDや救難信号を発信する仕組みで、これをセンサを備えた受信装置で受信し、電気信号に変え更に光信号に変えて、単独の専用光ケーブルで伝送するか?Multiplexerを介して、従来の計画されている光ケーブルに重畳して伝送するか、そして地上の基地局に伝送するシステムである。 図9(b)は、(a)と同様、発信源から発信された信号を受信し、単独あるいはMultiplexerにより信号を重畳して光ケーブルで基地局に伝送し、基地局で種々の目的の信号に選別判定する場合のシステムの実施例を示す。 船舶の接近や場合によってはケーブルの破壊の目的で航行して来た場合夫々のセンシング地点で特徴点や映像を捉えることにより敵の侵入を撮影したり破壊された場合でも敵船の特徴や場所を把握できることの説明図である。センサケーブルのセンサ部は短スパンで取り付けられており、主ケーブルの中継器の長さとは関係がない。 【0018】 図10(a)には、見出したい対象物をTarget1とする。Target1に対して、海底センサ列が信号を受信して、基地局でこの信号を分析する場合の解析法を示す。 光ケーブルに定距離で設置されているセンサナンバーと距離や位置はあらかじめ分かっている。センサナンバーが異なって敷設されていることも分かっており、センサナンバーをn番目とし、n+1番目、n+2番目やn−1番目等のセンサにTarget1から発せられた信号が受信されたとすると夫々のセンサに信号が到達する時間差が距離によって異なる。また、定まった間隔で設置されたセンサ間の距離や位置はあらかじめ分かっている。 それによって、Target1から発信された信号はn+2番目のセンサに受信されるに当って、Target1から発信された信号が到達するには距離Rn+2時間tn+2を要する。n+1地点の場合には同様に距離Rn+1時間tn+1を要する。n点の場合には距離Rn、時間tnを要する。夫々のセンサ位置は分かっており、海中の音波の伝播速度も分かっているので2点だけでも?円の円周の位置上にあることは計算で判明する。 図によると信号が到達しているのが4点であるのでより正確に位置決めができる。 この図の説明では、ケーブルが一直線上に配置されているので、この線をz軸とすると線(z軸)から直角にR6の距離の円周上にTargetが存在することが分かる。 このTargetが止まっている場合は、平円上の何処かに存在する筈である。 動作している場合にはz軸上のspeed U2が観測されるが、船舶側からの機械音等はDoppler効果により船舶のspeedが解析できる。 止まっている場合には状況判断ではあるが、海底のケーブルから直角に距離R0の左、ないしは右の2点に沈んでいると判断できる。 センサが多数あるので航行した軌跡も分かるのでTargetの位置も判別できる。 また、先の図にあるように無人潜水艇や海上の船に備えられたセンサによってもTargetから発せられた信号を受信するのでTargetの位置や存在をより正確に知ることが出来る。 図10(b)は、センサを網目状に配置する場合の例を示すもので、海底に横たわっている時には平面状の2次元センサを構成するのだが、実際にケーブルとしてドラム等に巻いて収納したり運搬するのには不可能なので陸上艦上にあるときはy方向に線を巻いてx方向のパイプないしは円筒状の線として構成し、水中に投じ沈めた状態で平面状に開くように形状記憶合金(プラスチック等でy方向の支線のみ曲げに強いプラスチックケーブルを使用して敷設する場合の実施例を示す。 【0019】 図11には、海難事故救助を含めての音波デバイスを受信するためのセンサ装置のみならず種々の振動音も受信できる装置を備え、その中でも人為的に作られた信号、例えば船舶のスクリュー音、エンジンの回転音やピストンの動作音、回転や走行により発生するキャピテーション音、その他人間が作った機械類の人為的な音、海底や海中の自然活動による発生音、海底トラフやマグマの移動や振動により惹起される振動や音波現象等を受信しケーブルを通じたり、中継潜水艇を介したり、基地局あるいは海上の船舶で分析し対応できるシステムを構築する。 人が搭乗する船舶、航空機、ヘリコプターの事故に対応して、ID信号の発生により事故現場の所在、個の発見を行うが人為的な設備、インフラの防衛も重要であり、地震、津波の予知も重要である。洪水や風害をもたらす台風や大雨の予報等も重要な情報源を得ることができる。 【0020】 図12には、センサユニットによる信号を単独で構築する場合を図12(a)に示し、他の地上間を結ぶ光ケーブルの空きチャンネルまたは余剰ケーブルを用いて、またMultiplexerを介して光ケーブルに重畳信号として合成し地上局等に伝送する方式を示す。 このような仕組みにより、新しいセンサネットワークシステムが構成することもでき、従来の方式を変えることなくシステムを構築することができる。 今後更に海底ケーブルを敷設するに当ってはセンサ付海底ケーブルとして構築する方が一石二鳥、三鳥となるので、単に大陸間や孤島との通信だけではなく海中、海底の様子、海難事故対応、海底ケーブル自体を守る総合的なネットワークを構築することができる。 【産業上の利用可能性】 【0021】 本発明により今迄暗中模索であった海の中が可成り可視化が可能となり、海の利用のみでなく陸上の人類、生物の生活の安全に役立つ新しい情報網の確立である。 【符号の説明】 【0022】 1.発信源(器) 2.緊急信号 3.コマンド 4.送受信装置(主に受信装置) 5.海上送受信 6.中継器 7.センサ中継器 8.主ケーブル(海底ケーブル) 9.分岐ケーブル(海底分岐ケーブル) 10.センサケーブル 11.ステーション(Cellar station) 12.陸上ステーション(陸上情報ステーション(地上局)) 20.中継器(外装含む) 21.中継器(基地局よりup link) 22.中継器(基地局よりdown link) 41a.トランスデューサセンサ(集音装置) 41b.全方向集音装置 41c.単指向性パラボラ集音装置 61.独立無人潜水艇 (62.ケーブル付潜水艇) 70.海上船 80.航空機、ヘリコプター 90.衛星 発信源も集音装置も既存のものまたは強力のものを用いる。既に開発されている受信装置はできるだけ用いる。 腰のベルトに取り付ける送信装置は音波や振動が遠くまで届くように強力なものを用いる。 腕に巻く形のものは小形化、軽量が必要である。 |
【図1】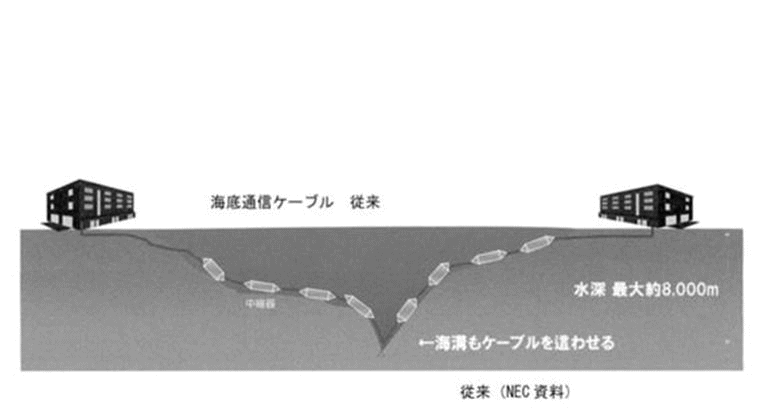 |
【図2】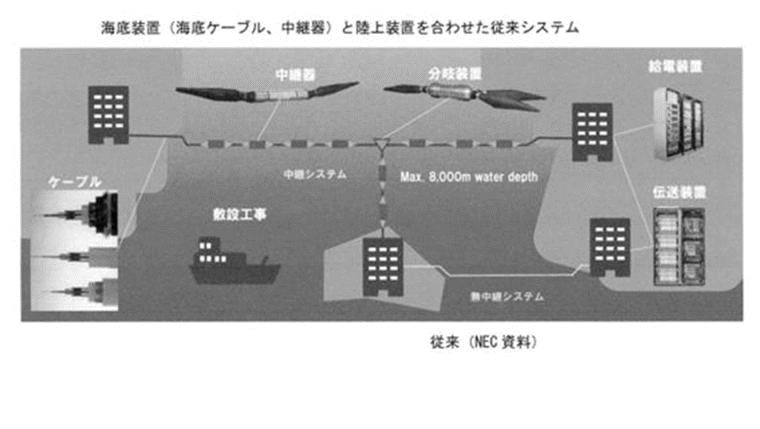 |
【図3】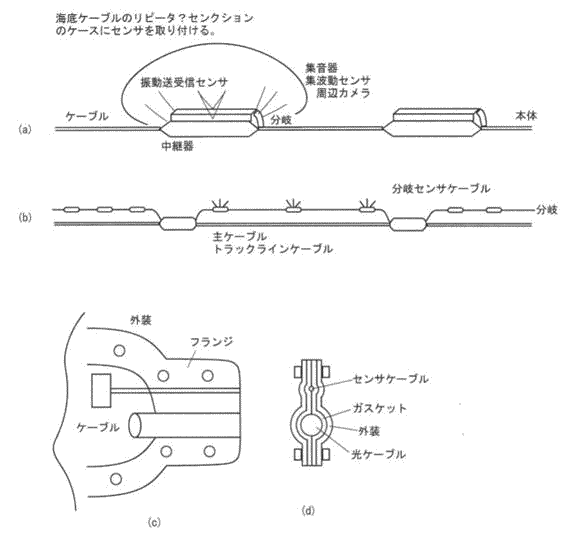 |
【図4】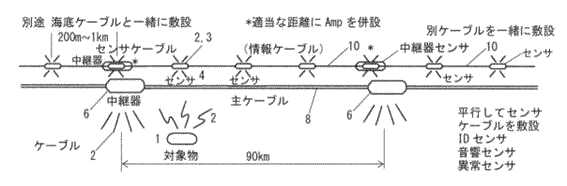 |
【図5】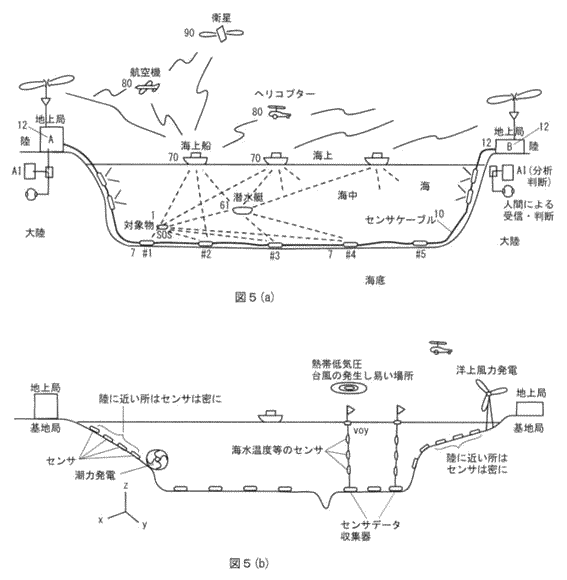 |
【図6】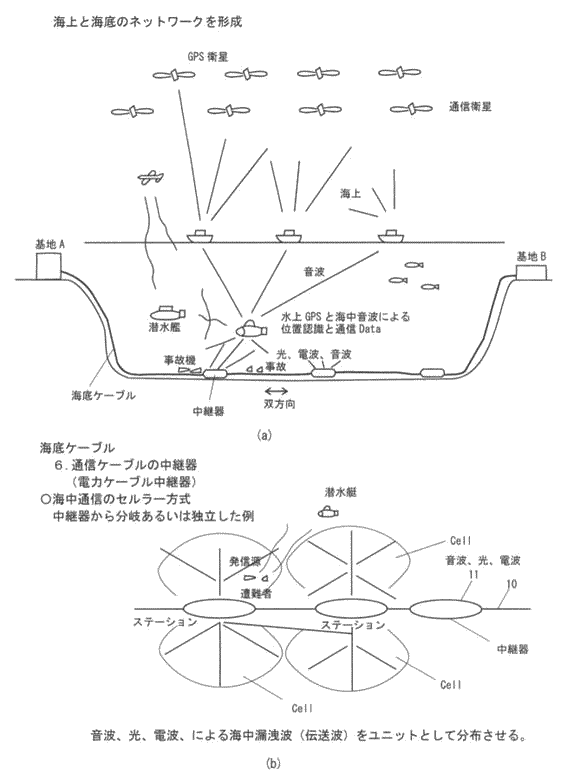 |
【図7】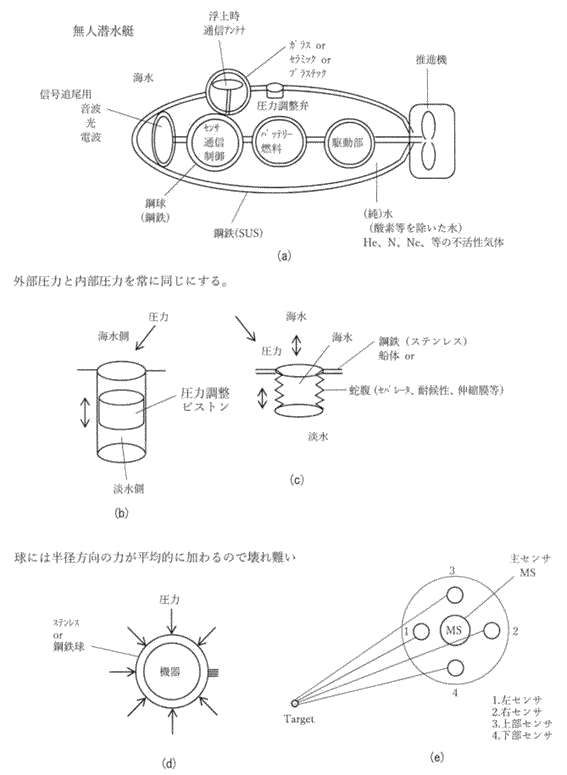 |
【図8】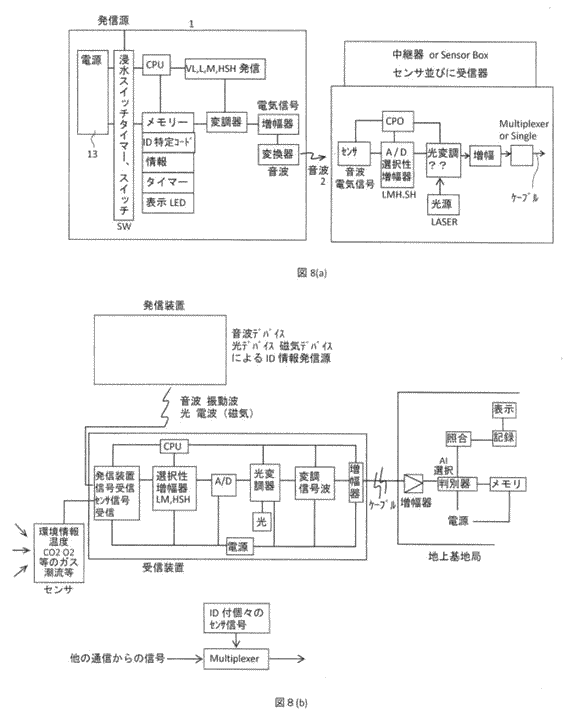 |
【図9】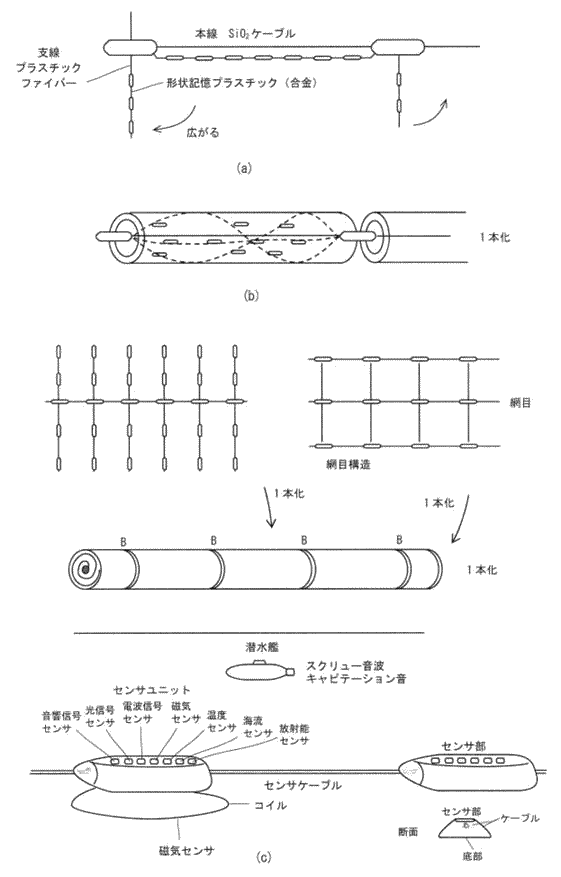 |
【図10】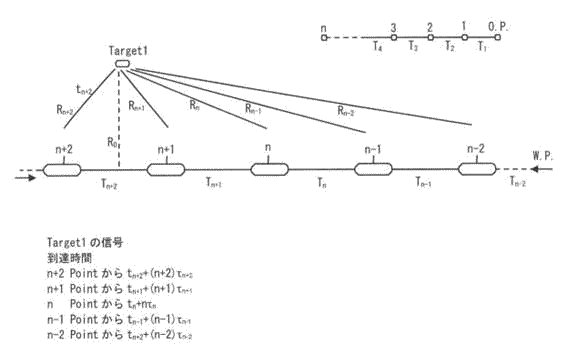 |
【図11】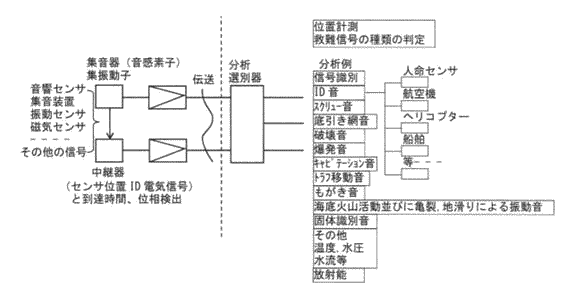 |
【図12】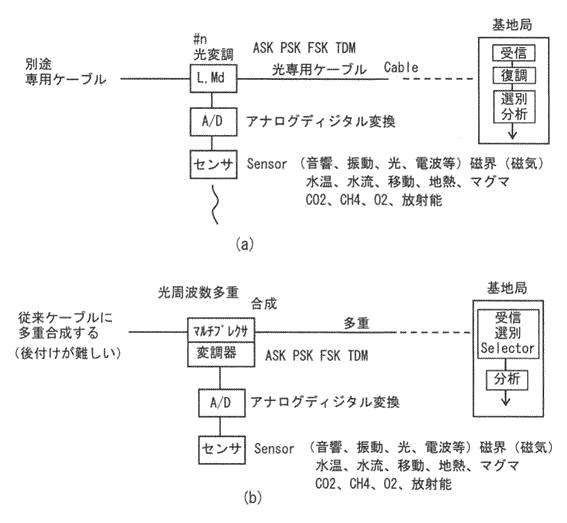 |
| ページtop へ |