| 閉じる | |
| 【意匠に係る物品】長襦袢 【意匠分類】B1−21 【国際意匠分類】Loc(14)Cl.2−02 【創作者】 【氏名】野中 恵実子 【住所又は居所】神奈川県横浜市泉区和泉町5627−1−401 【意匠権者】 【識別番号】524408252 【氏名又は名称】野中 恵実子 【住所又は居所】神奈川県横浜市泉区和泉町5627−1−401 【代理人】 【識別番号】100132517 【弁理士】 【氏名又は名称】山下 聡 【意匠に係る物品の説明】 本物品は、着物の下着として用いられる長襦袢である。長襦袢の衿(1)(又は地衿)は、首元で長襦袢に縫い付けられて、それ以外では長襦袢に縫い付けられておらず、ひらひらの状態となっている。長襦袢の衿(1)の衿先には、衿幅が当該衿(1)と同じで、深さが3ch程度のポケット(3)がある。 一方、長襦袢の他の部品として、半衿(2)が存在する(使用状態を示す参考図1)。半衿(2)は内部が筒状態となっており、中央付近で穴部(3)が存在する。長襦袢の衿(1)の先端から、半衿(2)の穴部(3)へ、衿(1)を通すことができる(使用状態を示す参考図2)。そして、長襦袢の衿(1)を半衿(2)の左右の筒部分に通し終えると、半衿(2)を長襦袢の衿(1)に取り付けることができる(使用状態を示す参考図3)。取り付けの際に、衿(1)の先端に設けられたポケット(3)に、物差しの先端を入れて、物差しを入れた状態で、ポケット(3)を半衿(2)の筒内に通すことで、簡単に、半衿(2)内に衿(1)を取り付けることができる。このように、半衿(2)を長襦袢の衿(1)に糸で縫い付けることなく取り付けることができるため、短時間で半衿(2)を長襦袢の衿(1)に取り付けることができる(使用状態を示す参考図4)。筒状の半衿は、何枚かあると交換できる。長襦袢はウェストベルトで押さえると、ひらひらの長襦袢の衿(1)を固定することができる(使用状態を示す参考図4)。 【意匠の説明】 長襦袢の衿が首元で長襦袢に縫い付けられ、それ以外では衿は長襦袢に縫い付けられておらずひらひらの状態となっている。 【参考文献】意登1139458 【参考文献】意登1410066 【参考文献】意登1724607 |
|
【正面図】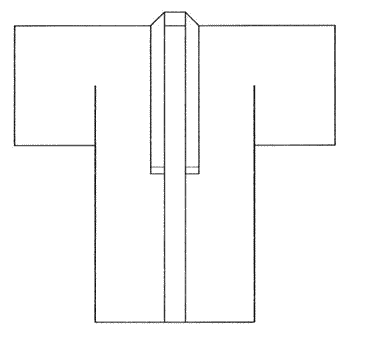 |
【背面図】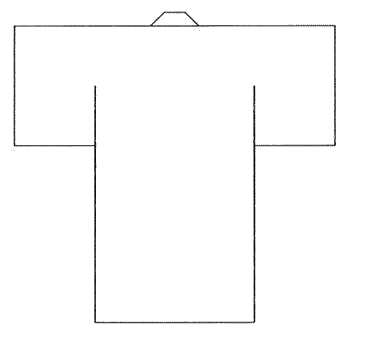 |
【右側面図】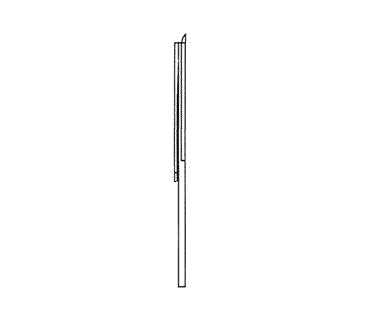 |
【左側面図】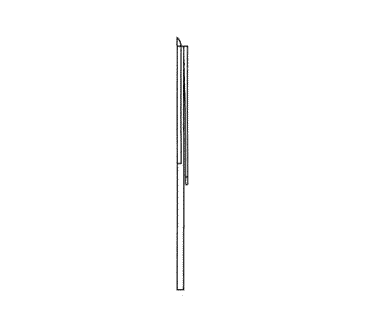 |
【平面図】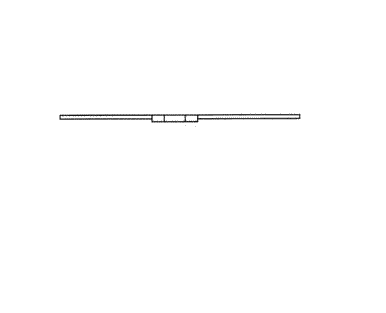 |
【底面図】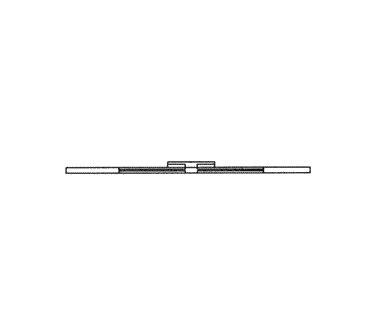 |
【使用状態を示す参考図1】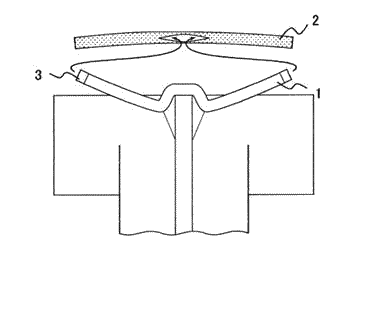 |
【使用状態を示す参考図2】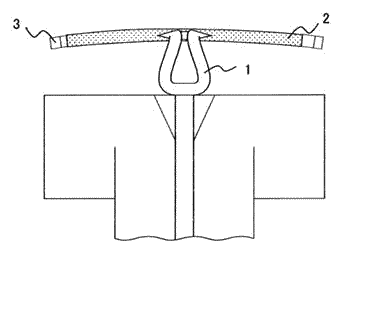 |
【使用状態を示す参考図3】 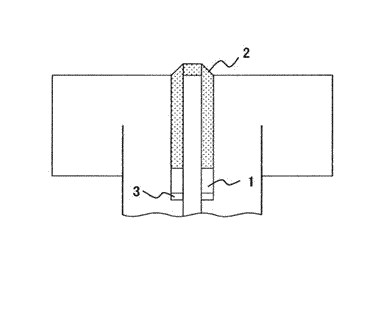 |
【使用状態を示す参考図4】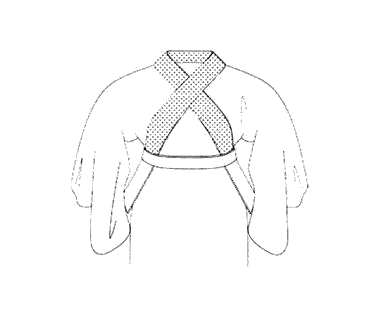 |
| ページtop へ |