| 閉じる |
| 【発明の名称】つる状多肉植物の製造方法 【早期審査対象出願】 【特許権者】 【識別番号】524191206 【氏名又は名称】野口 敏夫 【住所又は居所】千葉県香取郡東庄町笹川い4713-122 【代理人】 【識別番号】100148068 【弁理士】 【氏名又は名称】高橋 洋平 【発明者】 【氏名】野口 敏夫 【住所又は居所】千葉県香取郡東庄町笹川い4713-122 【要約】 【課題】多肉植物の植え替え前後においてその多肉植物の形状変化を楽しむことができるつる状多肉植物の製造方法を提供する。 【解決手段】本発明のつる状多肉植物1Bの製造方法は、多肉植物1Aにおける葉や茎などの柔組織部位2Aを多肉植物1Aから分離させる分離工程と、所定期間だけ柔組織部位2Aを乾燥させることによって柔組織部位2Aを巻き付ける(「ねじる」を含む)ことができる程度に柔組織部位2Aを軟化させた軟化柔組織部位2Bを生成する乾燥工程と、軟化柔組織部位2Bを巻き付ける巻付工程と、植付工程と、補水工程と、を備える。 【選択図】図4 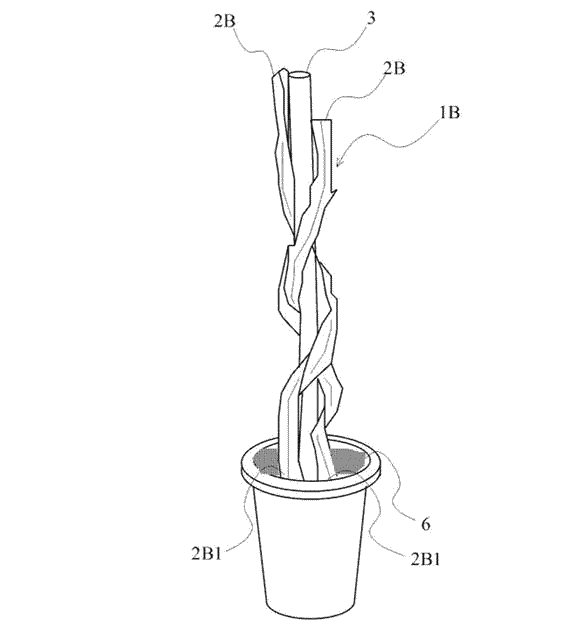 【特許請求の範囲】 【請求項1】 多肉植物における葉や茎などの柔組織部位を前記多肉植物から分離させる分離工程と、 所定期間だけ前記柔組織部位を乾燥させることによって前記柔組織部位を巻き付ける(「ねじる」を含む)ことができる程度に前記柔組織部位を軟化させた軟化柔組織部位を生成する乾燥工程と、 前記軟化柔組織部位を巻き付ける巻付工程と、 前記軟化柔組織部位の端部を用土に植える植付工程と、 前記巻付工程及び前記植付工程の後に前記軟化柔組織部位の端部に対して前記端部から根が生える程度に水分を補給する補水工程と、 を備えることを特徴とするつる状多肉植物の製造方法。 【請求項2】 前記多肉植物は、ドラゴンフルーツ(別名:ピタヤ)を例とするヒモサボテン(別名:サンカクサボテン)、又は、ゲッカビジンを例とするクジャクサボテンなど前記ヒモサボテンに対する近縁種サボテンであり、 前記柔組織部位は、葉状茎や茎節などの薄くて長尺状に形成された部位であり、 前記所定期間は、1〜2週間である ことを特徴とする請求項1に記載のつる状多肉植物の製造方法。 【請求項3】 前記補水工程後において前記軟化柔組織部位に対して1または2以上の接合口を作成する台木作成工程と、 前記接合口に対して同種又は他種の植物を用いて接ぎ木する接木接合工程と、 を備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のつる状多肉植物の製造方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、つる状多肉植物の製造方法に係り、特に、多肉植物をつる植物のようにらせん状又はコイル状に育成する際に好適に利用できるつる状多肉植物の製造方法に関する。 【背景技術】 【0002】 サボテンに代表される多肉植物においては、その一部を切り取って葉挿しなどの植え替えが行われることが一般的である。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】 特開2021−114915号公報 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、多肉植物の植え替えの場合、植え替え前の形状に基づいて植え替え後の多肉植物を育成するため、植え替え前後において見た目の変化を提供することができないという問題があった。 【0005】 そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、多肉植物の植え替え前後においてその多肉植物の形状変化を楽しむことができるつる状多肉植物の製造方法を提供することを本発明の目的としている。 【課題を解決するための手段】 【0006】 (1)本発明のつる状多肉植物の製造方法は、多肉植物における葉や茎などの柔組織部位を多肉植物から分離させる分離工程と、所定期間だけ柔組織部位を乾燥させることによって柔組織部位を巻き付ける(「ねじる」を含む)ことができる程度に柔組織部位を軟化させた軟化柔組織部位を生成する乾燥工程と、軟化柔組織部位を巻き付ける巻付工程と、軟化柔組織部位の端部を用土に植える植付工程と、巻付工程及び植付工程の後に軟化柔組織部位の端部に対して端部から根が生える程度に水分を補給する補水工程と、を備えることを特徴とする。 【0007】 これにより、本発明のつる状多肉植物の製造方法は、直線状に伸びる柔組織部位をつる植物のようにらせん状に生育させることができる。 【0008】 (2)また、本発明のつる状多肉植物の製造方法は、多肉植物は、ドラゴンフルーツ(別名:ピタヤ)を例とするヒモサボテン(別名:サンカクサボテン)、又は、ゲッカビジンを例とするクジャクサボテンなどヒモサボテンに対する近縁種サボテンであり、柔組織部位は、葉状茎や茎節などの薄くて長尺状に形成された部位であり、所定期間は、1〜2週間であることが好ましい。 【0009】 これにより、本発明のつる状多肉植物の製造方法は、発明者が好適と考える程度に、柔組織部位を何重ものらせん状に生育させることができる。 【0010】 (3)また、本発明のつる状多肉植物の製造方法は、補水工程後において軟化柔組織部位に対して1または2以上の接合口を作成する台木作成工程と、接合口に対して同種又は他種の植物を用いて接ぎ木する接木接合工程と、を備えることが好ましい。 【0011】 これにより、本発明のつる状多肉植物の製造方法は、新しい観賞植物としてのつる状多肉植物に対して接ぎ木の技術を付加することができる。 【発明の効果】 【0012】 本発明のつる状多肉植物の製造方法によれば、直線状に伸びる柔組織部位をつる植物のようにらせん状に生育させることができるので、多肉植物の植え替え前後においてその多肉植物の形状変化を楽しむことができるつる状多肉植物の製造方法を提供するという効果を奏する。 【図面の簡単な説明】 【0013】 【図1】図1は、本実施形態の多肉植物の一例を示す概要図である。 【図2】図2は、本実施形態の分離工程後における柔組織部位の一例を示す概要図である。 【図3】図3は、本実施形態の乾燥工程後における柔組織部位の一例を示す概要図である。 【図4】図4は、本実施形態の巻付工程後及び植付工程後における柔組織部位の一例を示す概要図である。 【図5】図5は、本実施形態の台木作成工程後及び接木接合工程後における柔組織部位の一例を示す概要図である。 【発明を実施するための形態】 【0014】 以下、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法を説明する。 【0015】 本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、分離工程と、乾燥工程と、巻付工程と、植付工程と、補水工程と、を備えることを特徴とする。また、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、台木作成工程と、接木接合工程と、をさらに備えることが好ましい。 【0016】 [分離工程]分離工程においては、図1及び図2に示すように、本実施形態の実施者が多肉植物1Aにおける葉や茎などの柔組織部位2Aを多肉植物1Aから分離させる。 【0017】 ここで、「多肉植物1A」は、ドラゴンフルーツ(別名:ピタヤ)を例とするヒモサボテン(別名:サンカクサボテン)、又は、ゲッカビジンを例とするクジャクサボテンなどヒモサボテンに対する近縁種サボテンであることが好ましい。なぜならば、以下に示す柔組織部位2Aの条件に合致するためである。以下に示す柔組織部位2Aの条件に合致するのであれば、本実施形態の多肉植物1Aは上記したサボテン以外の多肉植物1Aであってもよい。 【0018】 「柔組織部位2A」は、多肉植物1Aの葉、茎または根などの各部位のうち、水などの貯蔵物質を多量に蓄える柔細胞がその内部に集合する部位である。ここで、本実施形態の柔組織部位2Aは、葉状茎や茎節などの薄くて長尺状に形成された部位である。柔組織部位2Aが薄くて長尺状に形成された部位であれば、そうでない形状(例えば棒状や球状などの肉厚形状)の柔組織部位2Aと比較して、1または2以上の巻き数のつる状(又はコイル状)に形成することが容易となる。 【0019】 「分離」とは、柔組織部位2Aを多肉植物1Aから「切り離す、ちぎる、剪定する」など、柔組織部位2Aを有する育成中の多肉植物1Aから何らかの手段(例えば剪定ばさみ)を用いてその柔組織部位2Aを分けて離すことである。 【0020】 [乾燥工程]乾燥工程においては、図3に示すように、本実施形態の実施者が所定期間だけ柔組織部位2Aを乾燥させることによって柔組織部位2Aを巻き付ける(「ねじる」を含む)ことができる程度に柔組織部位2Aを軟化させた軟化柔組織部位2Bを生成する。 【0021】 ここで、「巻き付ける」とは、「コイルばねのごとく、添え木3などの何らかの軸を中心としてその軸の周囲を回転しながら曲げる」ことを意味する。それに対して、「ねじる」とは、「濡れた布を絞るかのごとく、物の両端に逆向きの力が働くような回転方向に曲げる」ことを意味しており、添え木3など実在する何らかの軸を必要としない。本実施形態の場合、『柔組織部位2Aを巻き付ける(「ねじる」を含む)』とは、『軸の有無に関係なく柔組織部位2Aをある回転方向に曲げる』ことを意味する。 【0022】 「所定期間」は、多肉植物1Aから分離した柔組織部位2Aが貯蓄する水などの貯蔵物質が消費や乾燥によって減少することにより、その柔組織部位2Aを巻き付けることができる程度に、柔組織部位2Aを軟化させる期間である。軟化させる前の柔組織部位2Aは水などの貯蔵物質を含んでいるために硬い。そのため、所定期間を経ることなく、軟化させる前の柔組織部位2Aを容易に曲げることはできず、強引に曲げようとすると柔組織部位2Aがねじ切れてしまう。発明者が本発明の開発から得られた経験上、その所定期間としては、1〜2週間が好ましい。 【0023】 [巻付工程]巻付工程においては、図4に示すように、本実施形態の実施者が軟化柔組織部位2Bを巻き付ける。この「巻き付ける」には、「ねじる」を含む意味である。そのため、本実施形態の巻付工程において、添え木3はあってもよいしなくてもよい。添え木3があったほうがないよりも観賞用としての見栄えはよくなる。添え木3を使用する場合の本実施形態の添え木3としては、従来から用いられる添え木3でよい。 【0024】 [植付工程]植付工程においては、図4に示すように、本実施形態の実施者が軟化柔組織部位2Bの端部2B1を用土6に植える。軟化柔組織部位2Bの端部2B1を用土6に植える理由は、従来から知られているように、その端部2B1から根が新たに生えるからである。 【0025】 [補水工程]補水工程においては、本実施形態の実施者が巻付工程及び植付工程の後に軟化柔組織部位2Bの端部2B1に対して端部2B1から根が生える程度に水分を補給する。 【0026】 [台木作成工程]台木作成工程は、図5に示すように、本実施形態の実施者が補水工程後において軟化柔組織部位2Bに対して1または2以上の接合口4を作成する。 【0027】 [接木接合工程]接木接合工程は、図5に示すように、本実施形態の実施者が接合口4に対して同種又は他種の植物を用いて接ぎ木5を接合する。接ぎ木5としては、多肉植物1Aの観照的統一性を求めるのであればハコボサボテンなどの多肉植物の芽を利用することが好ましい。 【0028】 次に、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法の効果を説明する。 【0029】 (1)本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、多肉植物1Aにおける葉や茎などの柔組織部位2Aを多肉植物1Aから分離させる分離工程と、所定期間だけ柔組織部位2Aを乾燥させることによって柔組織部位2Aを巻き付ける(「ねじる」を含む)ことができる程度に柔組織部位2Aを軟化させた軟化柔組織部位2Bを生成する乾燥工程と、軟化柔組織部位2Bを巻き付ける巻付工程と、軟化柔組織部位2Bの端部2B1を用土6に植える植付工程と、巻付工程及び植付工程の後に軟化柔組織部位2Bの端部2B1に対して端部2B1から根が生える程度に水分を補給する補水工程と、を備えることを特徴とする。 【0030】 これにより、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、直線状に伸びる柔組織部位2Aをつる植物のようにらせん状に生育させることができる。 【0031】 (2)また、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、多肉植物1Aは、ドラゴンフルーツ(別名:ピタヤ)を例とするヒモサボテン(別名:サンカクサボテン)、又は、ゲッカビジンを例とするクジャクサボテンなどヒモサボテンに対する近縁種サボテンであり、柔組織部位2Aは、葉状茎や茎節などの薄くて長尺状に形成された部位であり、所定期間は、1〜2週間であることが好ましい。 【0032】 これにより、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、発明者が好適と考える程度に、柔組織部位2Aを何重ものらせん状に生育させることができる。 【0033】 (3)また、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、補水工程後において軟化柔組織部位2Bに対して1または2以上の接合口4を作成する台木作成工程と、接合口4に対して同種又は他種の植物を用いて接ぎ木5する接木接合工程と、を備えることが好ましい。 【0034】 これにより、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法は、新しい観賞植物としてのつる状多肉植物1Bに対して接ぎ木5の技術を付加することができる。 【0035】 すなわち、本実施形態のつる状多肉植物1Bの製造方法によれば、直線状に伸びる柔組織部位2Aをつる植物のようにらせん状に生育させることができるので、多肉植物1Aの植え替え前後においてその多肉植物1Aの形状変化を楽しむことができるつる状多肉植物1Bの製造方法を提供するという効果を奏する。 【0036】 なお、本発明は、前述した実施形態などに限定されるものではなく、必要に応じて種々の変更が可能である。 【符号の説明】 【0037】 1A 多肉植物 1B つる状多肉植物 2A 柔組織部位 2B 軟化柔組織部位 2B1 (軟化柔組織部位の)端部 3 添え木 4 接合口 5 接ぎ木 6 用土 |
 |
 |
 |
【図1】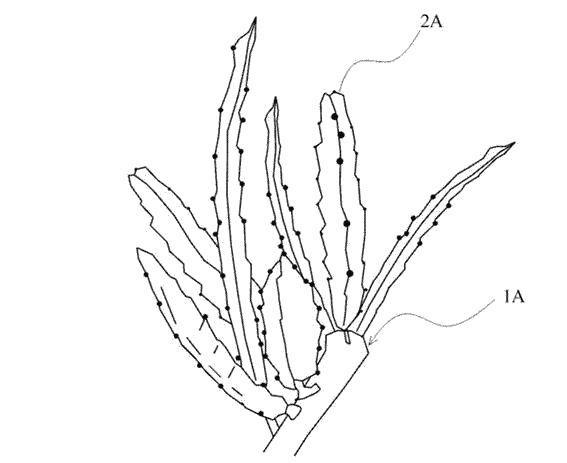 |
【図2】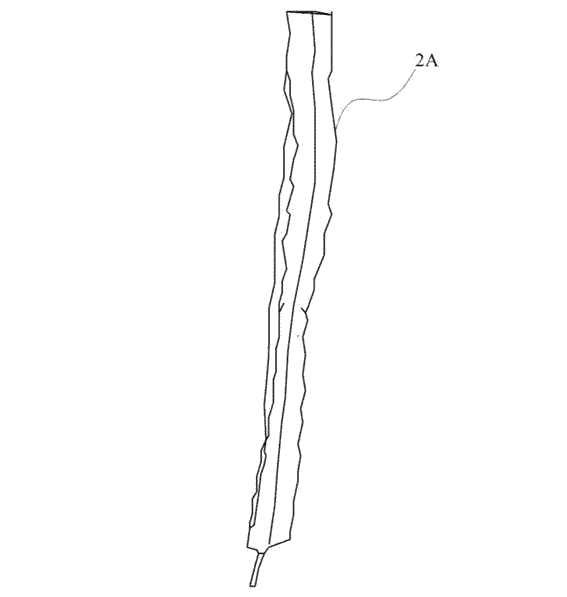 |
【図3】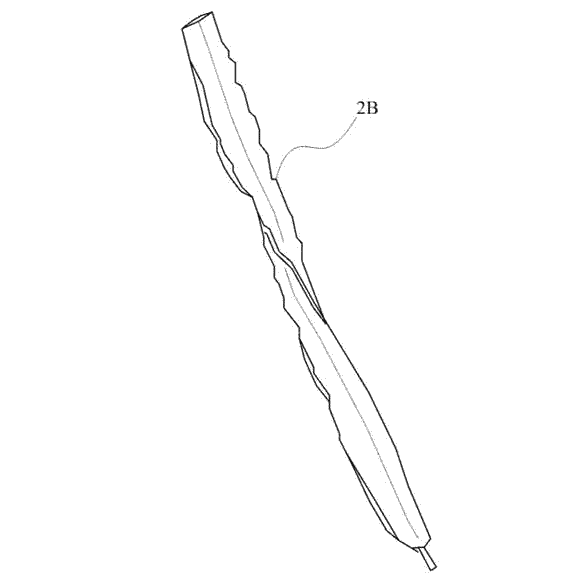 |
【図4】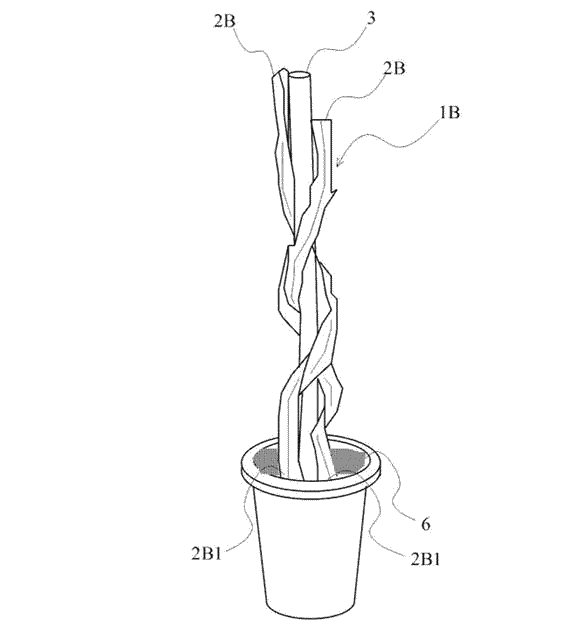 |
【図5】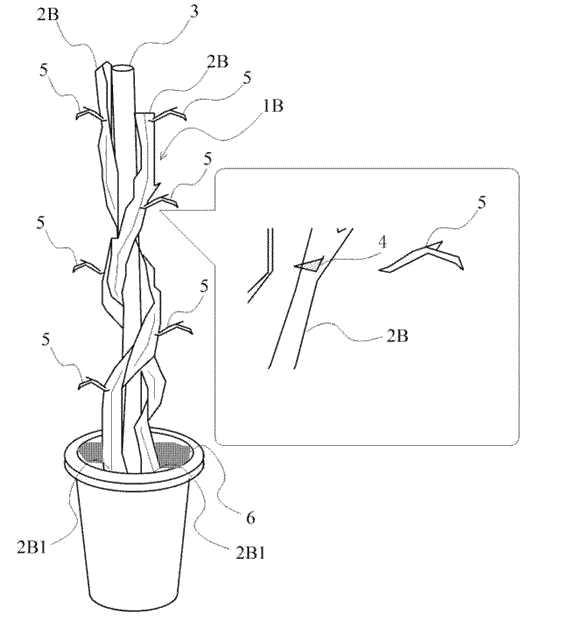 |
| ページtop へ |