| 閉じる |
| 【考案の名称】立体の頂点、辺、面などに関する学習用教材 【実用新案権者】 【識別番号】525149174 【氏名又は名称】小松 雅樹 【住所又は居所】秋田県湯沢市元清水2丁目5番31号 【考案者】 【氏名】小松 雅樹 【住所又は居所】秋田県湯沢市元清水2丁目5番31号 【要約】 【課題】本考案は、プラスチック製のジョイントとストローでつくる立体図形で、透明シートで覆って、立体の頂点、辺、面やそれらの関係を理解する学習用教材である。 【解決手段】プラスチック製のジョイント1にストロー2を差し込みストローの反対側にはジョイント差し込んで立体図形をつくり、立体の頂点、辺、面の数や辺と辺の並び方や交わり方を理解するのに役立つ。さらに、透明展開シートで覆うことにより、面の数や辺と面、面と面の並び方や交わり方を理解するのに役立つ。また、透明シートの利点を生かして、見取り図をかくときの見えない頂点や辺の位置の理解、面を紙に写取ってつなぎ合わせることで、展開図を正しくかくための理解に役立つ。 【選択図】図2 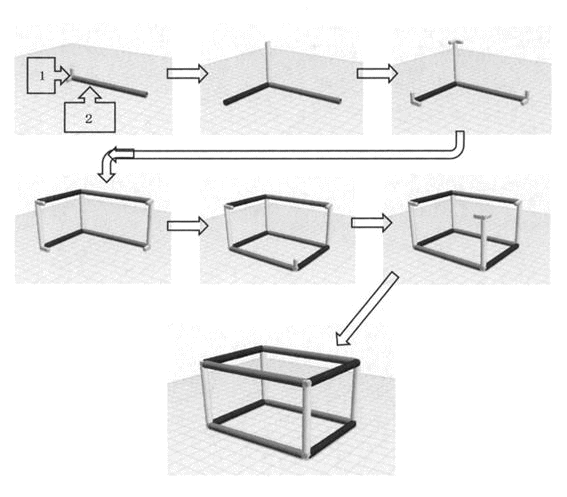 【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 立体図形の頂点からX軸Y軸Z軸の3方向に伸びたジョイント部分(断面を八角形にすることにより円柱形のストローが抜き差ししやすい)と、立体図形の辺にあたるストローから成り、ジョイント部分とストローを接続してできた立体図形から、直方体や立方体の辺や頂点の数、辺と辺の並び方や交わり方を理解するための立体図形学習用教材。 【請求項2】 前記立体図形を包み込むように折り曲げた透明な展開シートで覆い、面の数や面と辺、面と面の並び方や交わり方を理解するための請求項1記載の立体図形学習用教材。 【考案の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本考案は、立体図形学習用の教材に関し、立体を構成する頂点や辺、面などについて、それらを接続し組立てながら学習するために使用される。 【背景技術】 【0002】 従来、小学校の教育課程に於いて、直方体や立方体その他の多面体等の様々な立体図形の学習が要求されている。そして、立体図形の学習では、立体図形を構成する頂点や辺、面の数、辺と辺の交わり方や並び方、辺と面の交わり方や並び方、見取り図や展開図のかき方などを理解することが課題の一つになっている。 【0003】 ところが、一般に教科書等では、三次元からなる立体図形を二次元である平面図形、例えば見取り図に置き換えて表現しているため、児童にとっては立体図形を空間的に把握することが難しい。そのため、教育現場では、実際の箱から面を写し取って直方体や立方体を組立てたり、粘土玉を頂点に、竹ひごを辺として直方体や立方体を組立てたりして、頂点や辺、面の数、辺と辺の交わり方や並び方、辺と面の交わり方や並び方、見取り図や展開図のかき方などを理解してきた。 【考案の概要】 【考案が解決しようとする課題】 【0004】 しかし、上述したような方法では、学習者一人一人が立体図形を学習する上で不便である。面を写し取る箱は学習者が自宅から持参する場合が多く、大きさも形も様々で面を写し取りにくい。また、粘土玉と竹ひご又はプラスチックの棒で作った立体図形は不安定で変形しやすく、直方体や立方体の形にするまで時間がかかり、さらにそれを持ち上げて色々な方向から観察することは極めて困難である。そのため、立体図形を構成する諸要素について理解することが難しいという問題点があった。 【課題を解決するための手段】 【0005】 そこで、請求項1記載の立体図形学習用教材は、上述した従来技術の問題点に鑑みて作製されたものであり、その目的は、立体図形を構成する頂点や辺の数、辺と辺の並び方や交わり方を実感的に理解することができ、見取り図をかく時にも辺と辺の関係を容易に把握できる学習効果の高い教材を提供するものである。 【0006】 これに加え、請求項2記載の透明な展開シートで覆うことにより、立体の面と辺や面と面の並び方や交わり方を容易に理解することができ、展開図をかく時にも面と面の関係を把握するのが容易になり、学習効果をより一層高めた教材を提供するものである。 【考案の効果】 【0007】 本考案は、ジョイント部分がプラスチック製で、接続部がX軸Y軸Z軸方向に伸びているので、8個のジョイントと12本のストローを接続してできる直方体や立方体は、軽く、形態が安定していて、色々な角度から観察しながら立体図形を構成する頂点や辺、面の数、辺と辺の並び方や交わり方を学習するのに役立つ。 【0008】 それに加え、透明な展開シートで覆うことにより、面の数、辺と面の並び方や交わり方、見取り図や展開図のかき方を学習するのに役立つ。 【図面の簡単な説明】 【0009】 【図1】断面が八角形のジョイント 【図2】ジョイントとストローを接続してできる立体図形 【図3】上記の立体図形を透明な展開シートで覆った立体図形 【考案を実施するための形態】 【0010】 直方体の頂点部分を構成する断面が八角形のジョイントに、辺にあたるストローを差し込んで、直方体の形を作っていく。学習者は、作っていく過程や作ってからの観察を通して、立体図形の構成要素(頂点や辺の数など)、辺と辺の並び方や交わり方などの性質を調べて学んでいく。 【0011】 請求項2記載の透明な展開シートで覆うことにより、学習者は、面の数、辺と面、あるいは面と面の並び方や交わり方について調べて学んでいく。 【実施例】 【0012】 以下、添付図面に従って一実施例を説明する。[図1]の1は立体図形の頂点を兼ねたジョイント部分で、ここの凸部にストローを差し込んでいく。[図2]の要領で、3種類の長さのストロー(各4本)をジョイントの凸部に差し込んでいくが、一つのジョイントに3種類あるストローをそれぞれ1本ずつ差し込むことが大切である。その後、ストローの反対側にはジョイント差し込み、その凸部にストローを差し込んでいく。このとき、向かい合った辺が同じ長さのストローになるようにすることが大切である。この組立て作業を試行錯誤しながら行うことで、学習者自身が直感的に直方体の形をとらえていくことができる。そして、組立て終了後に、辺や頂点の数、同じ長さの辺の数やそれが何組あるか確認できる。さらに、辺と辺の並び方や交わり方を、見方を自由に変えながら学んでいくことができる。 【0013】 組立てた[図2]の直方体に[請求項2]の透明な展開シートで覆うと、[図3]のように、立体図形の面が形成され、面の数や辺と面、面と面の並び方や交わり方を学ぶことができる。学ぶ際には、透明シートに油性ペンで頂点や面を記号化して書込むと、具体的に調べることができる。また、この教材は透明シートで覆われているため、実際の直方体では見えない部分の辺や頂点の位置も確認できる。これにより学習者が、正しい見取り図をかくことができるようになる。さらに、立体の各面を紙に写取り、つなげることで、展開図のかき方についても学ぶことができる。 【産業上の利用可能性】 【0014】 学校教育の現場で、児童一人一人がこの教材を用いて、立体図形について具体的、直感的に学ぶことができ、教育産業上大いに利用できる。 【符号の説明】 【0015】 1 立体図形の頂点を兼ねたジョイント 2 立体図形の辺に相当するストロー |
【図1】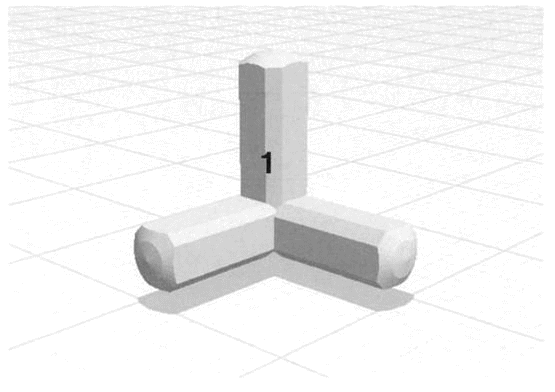 |
【図2】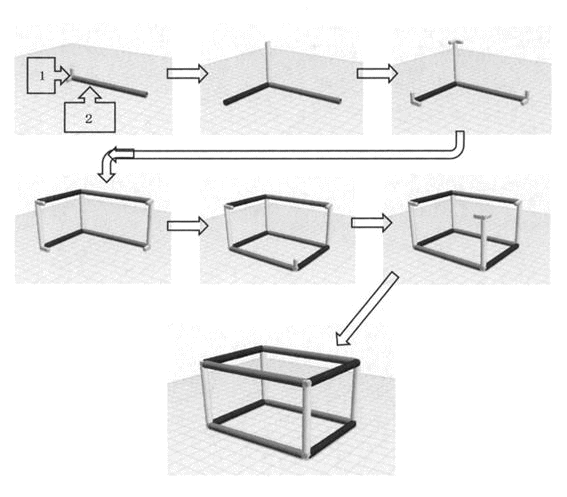 |
【図3】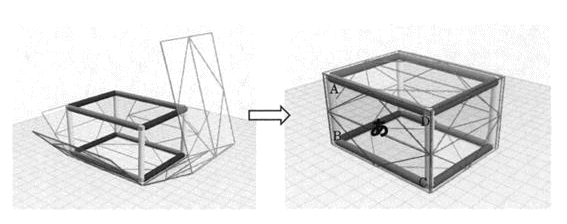 |
楽しく分かりやすい立体図形教材 本考案は、子どもが組立てながら立体の頂点や辺の数を確かめたり、辺と辺の垂直や平行の関係を理解したりするための教材です。そして、組立てた立体を透明展開シートで覆うことで、面の数や辺と面の垂直や平行、面と面の垂直や平行の関係もつかむことができます。 教科書の紙面のように立体を平面的に表したものや、バーチャルリアリティで立体を回転させて色々な角度から見ることのできる教材もありますが、実際に自分の目で見て触って体感できるところが、この教材の良さです。組立てた図形は、見取り図をかく際の参考にもなります。何よりも子ども自身が試行錯誤しながら自分で組立て、自分で色々な角度から眺めることで、立体図形への理解を深め、センスを養うことが大切なのだと思います。このように、立体図形を実感的にとらえられることは、バーチャル体験ではできないことです。 日本全国の先生方がこの教材を使って、立体図形の楽しさや面白さを子ども達に伝えてくれることを願っています。 |
| ページtop へ |