| 閉じる |
| 【考案の名称】ペン立てケース 【実用新案権者】 【識別番号】324008180 【氏名又は名称】坂田 美純 【住所又は居所】京都府京田辺市大住責谷74-37 【考案者】 【氏名】坂田 美純 【住所又は居所】京都府京田辺市大住責谷74-37 【要約】 (修正有) 【課題】ペンの太さが異なる場合も使用することができ、ペンの整理整頓を行うことができるペン立てケースを提供する。 【解決手段】斜面2aが設けられた土台2と、斜面2aと所定間隔を隔てて対向して配置されるとともに水平方向に配置される天板3と、土台2と天板3とを連結する連結板4とを備え、天板3には、ペンを挿すための開口幅が異なる複数の孔部6が設けられており、土台2には、ペン先を配置するための複数の凹部5が設けられている。 【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 斜面が設けられた土台と、前記斜面と所定間隔を隔てて対向して配置されるとともに水平方向に配置される天板と、前記土台と前記天板とを連結する連結板とを備え、 前記天板には、ペンを挿すための開口幅が異なる複数の孔部が設けられており、 前記土台には、前記ペン先を配置するための複数の凹部が設けられていることを特徴とするペン立てケース。 【請求項2】 前記複数の孔部は、少なくとも1以上の第1孔部と少なくとも1以上の第2孔部とを備え、 前記第1孔部の開口幅が10mmおよび前記第2孔部の開口幅が13mm、または、前記第1孔部の開口幅が12mmおよび前記第2孔部の開口幅が15mmであることを特徴とする請求項1記載のペン立てケース。 【請求項3】 前記天板には、複数の前記第1孔部が並列して配置されており、複数の前記第2孔部が並列して配置されていることを特徴とする請求項2記載のペン立てケース。 【考案の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本考案はペン立てケースに関する。 【背景技術】 【0002】 ペンは、料理のレシピをメモしたりガソリン代の計算をしたりする場合に、使用される。この場合、ペンが机の上に散らばることがある。ペンを収納するためのものとして例えば特許文献1記載のペン立てがある。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】 特開2020−192693号公報 【考案の概要】 【考案が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、特許文献1記載のペン立ては、ペンを1本1本収容するものではないので、取り出しにくいという難点がある。一方、ペンを1本ずつ収容するタイプのペン立ては、ペンの大きさによってはペン立てに入らない可能性がある。 【課題を解決するための手段】 【0005】 このような課題を解決するために、本考案のペン立てケースは、斜面が設けられた土台と、前記斜面と所定間隔を隔てて対向して配置されるとともに水平方向に配置される天板と、前記土台と前記天板の一端とを連結する連結板とを備え、前記天板には、ペンを挿すための開口幅が異なる複数の孔部が設けられており、前記土台には、前記ペン先を配置するための複数の凹部が設けられていることを特徴とする。 【考案の効果】 【0006】 上述のように構成した本考案のペン立てケースは、天板に開口幅が異なる複数の孔部が設けられているので、ペンの太さが異なる場合であっても使用することができ、ペンの整理整頓を行うことができる。 【図面の簡単な説明】 【0007】 【図1】本実施形態のペン立てケースを示す斜視図。 【図2】本実施形態の天板を示す斜視図。 【図3】本実施形態の土台を示す斜視図。 【考案を実施するための形態】 【0008】 以下、本考案のペン立てケースの実施形態について図面を使用しながら説明する。 【0009】 本実施形態のペン立てケース1は、図1に示すように、斜面2aが設けられた土台2と、斜面2aと所定間隔を隔てて対向して配置されるとともに水平方向に配置される天板3と、土台2と天板3とを連結する連結板4とを備える。 【0010】 土台2は、図1及び図3に示すように、略三角柱形状をなすものであって、軸方向が水平方向となるように配置され、水平位置から斜め方向をなす斜面2aが水平面上に配置されて、この斜面2aにペン先を配置するための複数の凹部5が設けられている。具体的に本実施形態では、土台2は軸方向に130mm、鉛直方向に2.75mm、水平方向に45mmとなるように構成されている。また、凹部5の開口幅は4mmとなるように構成されている。 【0011】 天板3は、図1及び図2に示すように、土台2から鉛直方向に所定間隔(本実施形態では水平面から55mm)隔てて配置されており、矩形状をなす板体で構成されて、長手方向が130mm、短手方向が45mmとなるように構成されている。 【0012】 また、天板3にはペンを挿すための開口幅が異なる複数の孔部6が設けられており、本実施形態では開口幅が12mmとなる複数の第1孔部6aと、開口幅が15mmとなる複数の第2孔部6bが設けられている。開口は略円形状をなしている。なお、この第1孔部6aの大きさを10mm、第2孔部6bの大きさを13mmとなるように構成してもよい。第1孔部6a及び第2孔部6bは、図1に示すように、それぞれ並列して配置されている。 【0013】 連結板4は、矩形状をなす板体で構成されて、直立して配置されるとともに、鉛直下方に配置される一端部が土台2の軸方向の一部に連結されて、鉛直上方に配置される一端部が天板3の長手方向の一端部に連結されている。 【0014】 このように構成された本実施形態のペン立てケース1は、天板3に開口幅が異なる複数の孔部6(第1孔部6aおよび第2孔部6b)が設けられているので、ペンの太さが異なる場合であってもペン立てとして使用することができ、ペンの整理整頓を行うことができる。 【0015】 なお、連結板は 土台の軸方向と直交する両端面と天板の短手方向に配置する両端部とをそれぞれ連結するように配置されていてもよい。 【0016】 本考案は、上記実施形態に限られることなく、その目的の範囲内で適宜変更して実施することができる。 【符号の説明】 【0017】 1・・・ペン立てケース 2・・・土台 2a・・・斜面 3・・・天板 4・・・連結板 5・・・凹部 6・・・孔部 6a・・・第1孔部 6b・・・第2孔部 |
料理のメーニュをメモします。ガソリン代の計算、買い物のレシトの計算でよくペンを使います。 机の上にペンが散らばります。整理整頓のために、ペン立てケースに刺しまとめることで部屋が整理され綺麗です! このペン立てケースは何本ものペンを収める事ができます。 ボールペン、鉛筆、色鉛筆を収められ、太いのペン、細いのペンも収める事ができます。 ご家庭、事務所、サービスカウンターいろんな場所に使え便利です! |
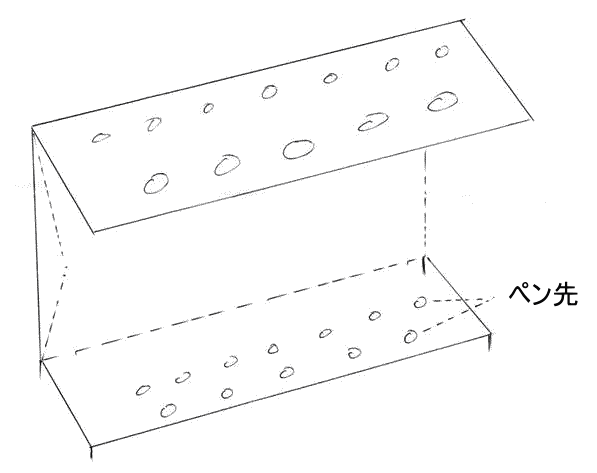 > > |
【図1】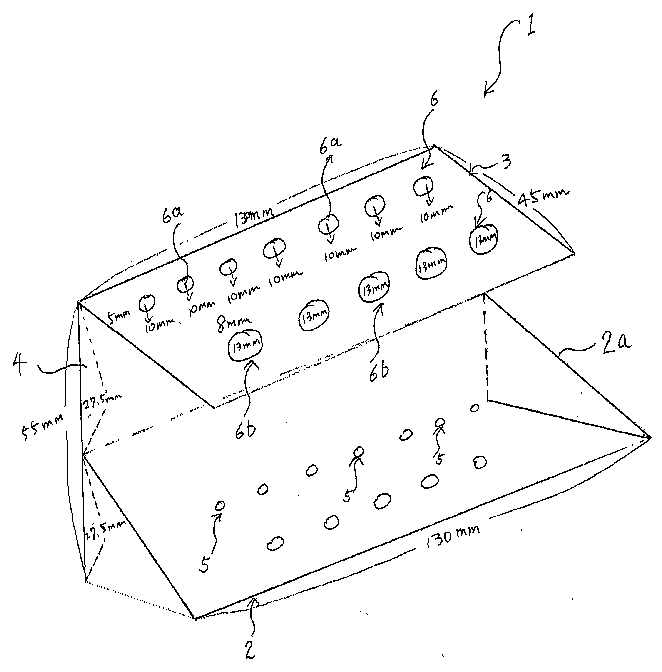 |
【図2】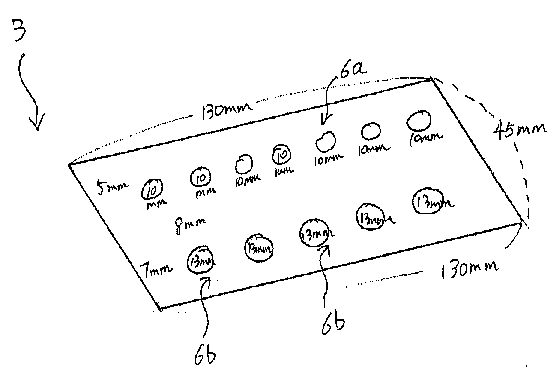 |
【図3】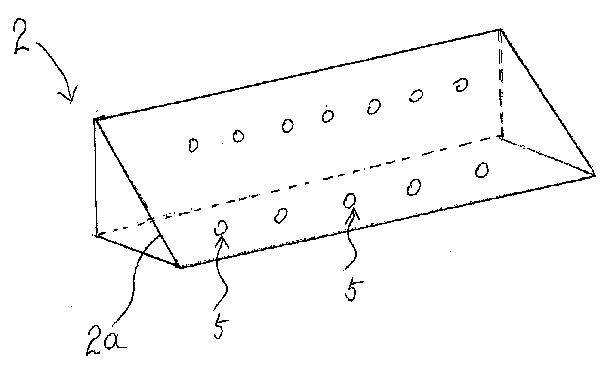 |
| ページtop へ |